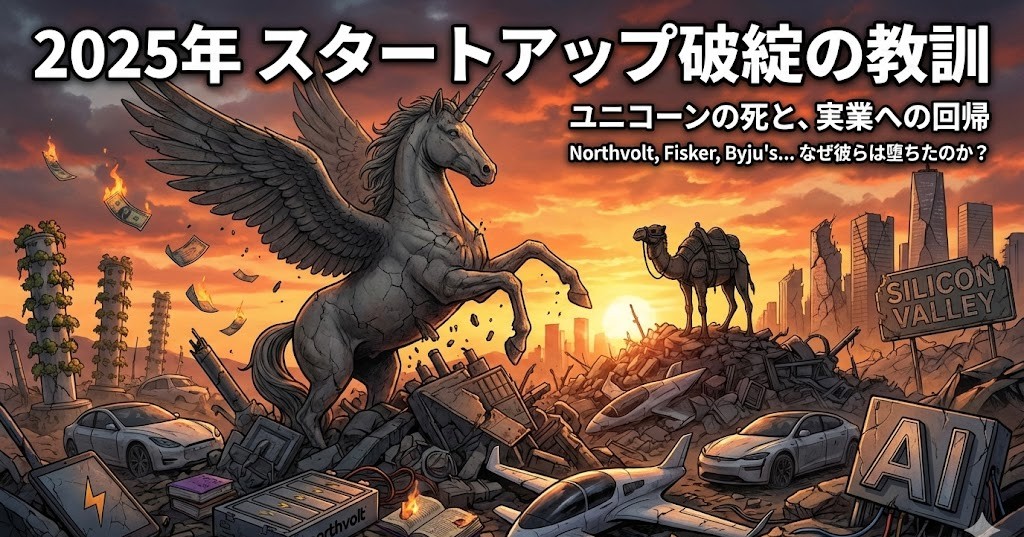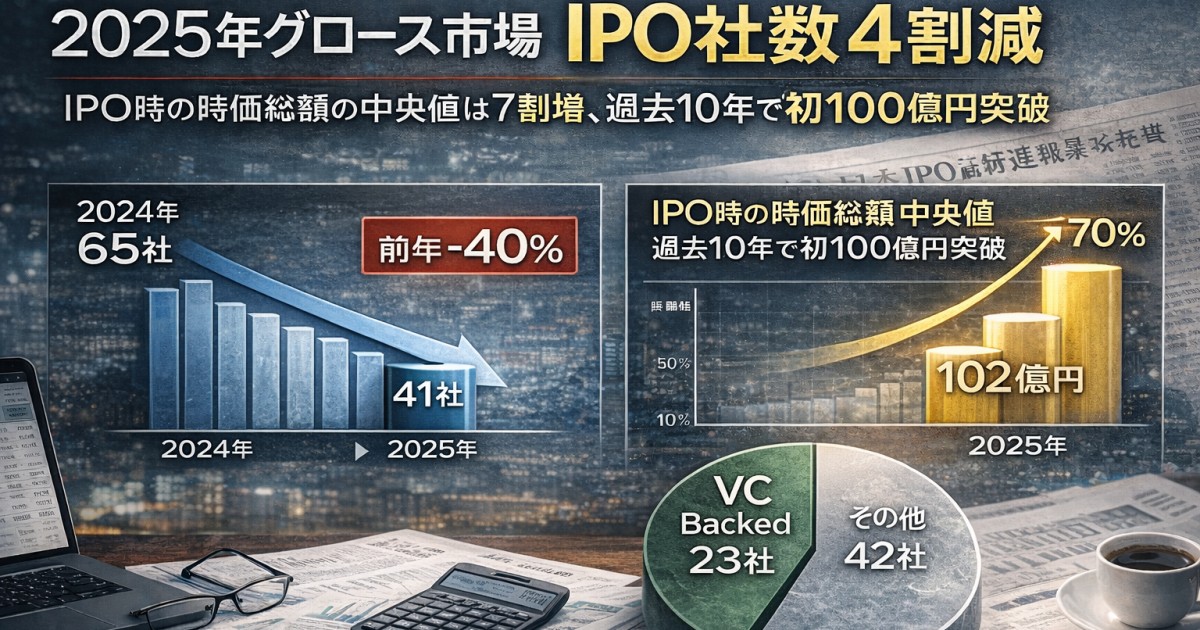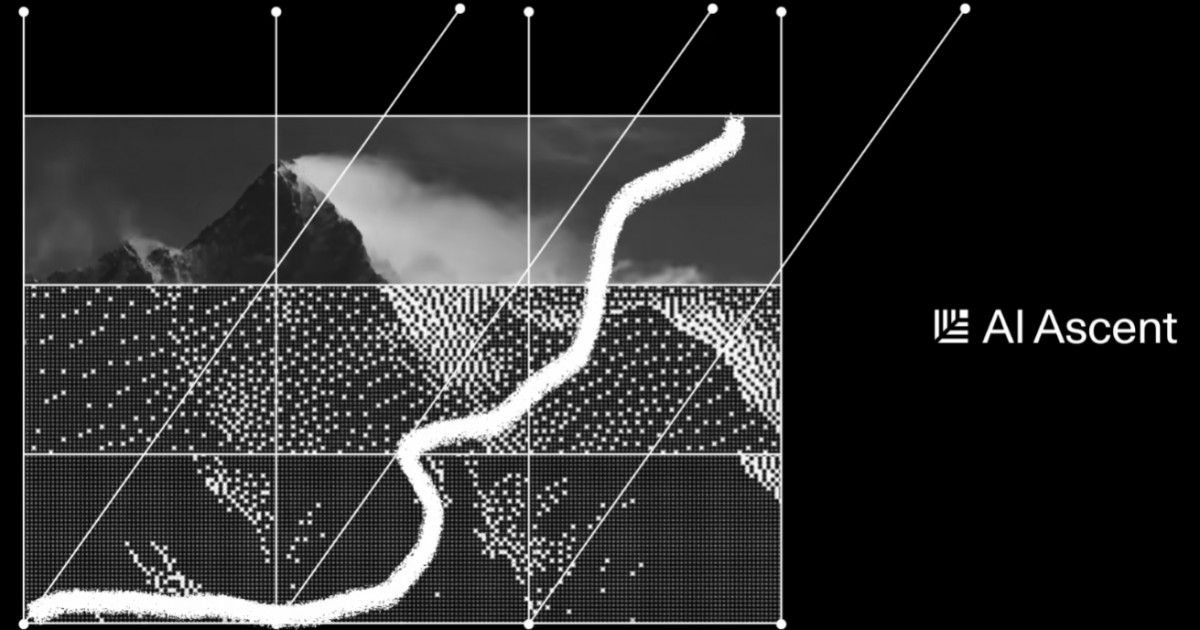歴史は繰り返す、産業の破壊と創造:スタートアップが活かせる共通項は何か?
私たちが「変化は緩やかに訪れる」と思いこんでいる間に、テクノロジーは一気に世界を変えてしまいます。鉄道が運河を、電灯がガス灯を、自動車が馬車を、スマートフォンが従来の携帯電話を。
本記事では、テクノロジーが市場を破壊する方法を歴史から解き明かし、次なる巨大な事業構想のヒントを探ります。
要約
-
世界は私たちが予想するよりも早く変化し、
その結果は私たちが予想するよりも遥かに大きくなる -
テクノロジーが世界を支配する方法は2つある
①直接的な置き換え(例:自動車 VS 馬車)
②市場の創出 or 統合(例:Uber VS タクシー) -
技術だけでは産業は変革できない
インフラや規制の整備、社会が受け入れるタイミングが重要
はじめに
歴史を通じて、様々な企業が新技術を活用して急速に市場シェアを拡大し、支配的な既存企業を追い抜き、または前例のない規模で新しい市場を創造してきました。
産業革命から21世紀に至るまで、飛躍的な技術革新、インフラの整備、革新的なビジネスモデル等を活用したスタートアップ(新興企業)によるイノベーションの速度はどんどん加速しており、また大きくなってきています。
本レポートでは、歴史を振り返り、イノベーションを2つのカテゴリーに分けて検証します。
(1)新しい技術を駆使した新規参入企業による既存企業の直接的な置き換え
(2)新しい技術によって以前は分断されていた、あるいは存在しなかった市場の創出 or 統合
以下の変革的な出来事において、移行がいかに早く起こったか、変化の背景にある実現要因、インパクトの規模(市場シェア、価値創造、リーチ)を考察し、共通項を導き出します。

Fifth Avenue Easter Parade in NYC, 1900年 (左の画像) vs. 1913年 (右の画像)
馬車が街を埋め尽くした1900年の五番街の写真と、たった13年後の1913年、同じ場所で自動車が溢れ馬車がたった1台になったこの写真。この劇的な変化は、テクノロジーが市場をいかに急速に塗り替えるかを如実に物語っています。
①直接的な置き換え
このケースでは、新しいテクノロジーによって、スタートアップ(新興企業)が市場リーダーとして君臨していた大手企業や、従来の生産・輸送手段を直接置き換えた事例を取り上げます。
鉄道 VS 運河と馬車(1830年代~1850年代)
19世紀初頭、蒸気機関車の技術を利用した鉄道は、運河や馬車に取って代わる主要な輸送手段として急速に普及しました。1830年に最初の主要鉄道(リバプール-マンチェスター間)が開通すると、鉄道路線は爆発的に拡大していきます。アメリカでは、1830年代だけで3,300マイルを超える線路が敷設され、これは既存の運河の全走行距離に匹敵します。
鉄道は、運河や馬車にはない輸送速度と年間を通じた安定性(時速10マイル以上、オールシーズン運行)を提供しました。1850年代までには、長距離の移動と貨物は鉄道が独占するようになり、馬車はほとんど姿を消しました。既得権益層(運河運営会社等)は当初抵抗し、列車による貨物輸送を禁止するロビー活動まで行いました。
しかし、鉄道輸送は拡大を続け、物資の輸送コストと時間を大幅に削減し、地域に限定されていた経済圏を全国に拡大し、わずか数十年のうちに、鉄道はほとんどの運河事業や馬車路線を時代遅れかニッチなものに置き換えました。これを可能にしたのは、蒸気機関技術の飛躍的な進歩、鉄道インフラへの大規模な資本投資、そして支援政策(アメリカにおける土地交付金など)でした。
その結果、19世紀の商業の基幹となる統一された交通網が生まれたのです。

電灯 VS ガス灯(1880年代~1900年代)
1800年代後半、電気照明技術(最初はアーク灯、次にエジソンの白熱電球と関連する電力システム)が、都市における照明の主流としてガス灯を急速に置き換えていきました。
ガス灯会社は19世紀の大半の間、道路や建物を照らしていましたが、ガス灯には火災の危険性、有害なガス、薄暗さといった欠点があり、優れた解決策を模索する必要がありました。故に、電灯は驚くべきスピードで普及します。最初の公共の電気街灯は1880年代に登場し、1920年代頃までには、ほとんどの都市部で主要な道路や施設がガスから電気照明に転換されました。
具体的には、1881年にロンドンのサボイ劇場に電灯が設置され、1890年代にかけての高圧交流配電の開発により、送電距離の問題が解決され、低コストの電力網の急速な成長が可能になり、 ガス照明が終焉しました。
数十年のうちに、エジソンのような電気事業者が照明市場でガス事業者を追い抜き、20世紀初頭には明らかに電気照明が優勢となりました。それを可能にした要因には、主要な発明(効率的な発電機、電球)、配電網インフラの整備、家庭や街路で電気を利用できるようにした安全性・規制の承認などがありました。

自動車 VS 馬車(1900年代~1910年代)
おそらく20世紀で最も象徴的な産業変革は、「自動車と馬車」でしょう。
1900年当時、市街地の道路は馬と馬車で埋め尽くされており、自動車は珍しいものでした。それからわずか20年後、状況は逆転します。冒頭の画像の通り、1900年と1913年のニューヨーク五番街は、1900年には自動車は1台だけだったのに対し、1913年には馬車は1台しか見当たりません。
この革命の中心となったのは、ヘンリー・フォードのT型自動車と動く組立ラインでした。フォードは1908年に信頼性が高く低コストの「大勢のための自動車」としてT型を発表し、継続的に価格を引き下げました。(1908年の850ドルから1920年代には300ドル以下まで)
当時の馬車の価格も1,800ドルから数百ドルしたことから、同等以下の価格水準でした。また、馬車は馬の排せつ物による衛生問題と、馬の飼育に係る維持コスト、平均速度の遅さによる長距離移動の不向きなど多くの問題を抱えていましたが、自動車が全てを解決してしまいます。
フォードの大量生産システムは爆発的な成長をもたらし、 米国の自動車市場におけるフォードのシェアは、1908年の9%から1921年までに61%に急上昇します。1910年代初頭までに、何千万人ものアメリカ人が仕事と旅行に自動車を利用するようになり、馬は街路から急速に姿を消しました。
この大変革はたった10年で起こりました。馬を使った数千年にわたる交通手段が根絶するには、驚くほど短い期間です。それを可能にした主な要因は、ガソリン内燃機関の技術革新、大量生産組立ラインの発明、拡大する道路インフラでした。これらにより、新規参入者(フォードをはじめとする自動車メーカー)は、コストと性能の両面で既存参入者(馬の生産者、ワゴンメーカー)を打ち負かすことができ、その結果、巨大な新市場(個人用自動車)が生まれ、馬車産業は崩壊しました。

コンピューター VS 計算機(1940年代~1960年代)
20世紀半ばのIBMの台頭は、新技術の波に乗ることで既存企業を駆逐したテック企業の典型です。
1910年代から1930年代にかけて、ビジネスデータ処理は機械式集計機(パンチカード式集計機)と手動式計算機が主流でした。IBM自身も、1910年代には小規模な企業としてスタートしましたが、トーマス・ワトソンのもと、パンチカード式集計機の研究開発と大規模生産に多額の投資を行い、優れた電気機械システムと積極的な販売・サービス組織を導入することで、IBMはレミントン・ランドの集計機やバローズの加算機といった初期の競合他社を着実に追い詰めていきます。
そしてIBMは、電子計算機の出現により、その競争力を加速させます。IBMは新しい技術(例えば、1953年のIBM 701、1964年の画期的なSystem/360)に賭け、レミントン・ランドのUNIVACのような先発メーカーをあっという間に追い抜いていきました。
1965年までに、IBMはコンピュータ市場の約65%を占め、「7人の小人」(バローズ、スペリーランド、ハネウェルなど)が残りを分け合いました。この圧倒的勝利は、商用コンピュータの登場からおよそ10年か20年のうちに達成されました。IBMの台頭は、莫大な研究開発費による技術革新(機械式コンピューティングから電子式コンピューティングへの移行)、莫大な研究開発費とインフラ設備投資、重要な補完要素(ソフトウェア、周辺機器、全国的なサービス能力)の管理によって成されました。IBMは1960年代に時価総額で世界最大級の企業となり、コンピューター時代への移行を象徴する存在となりました。

②市場の創出 or 統合
2つ目のケースは、既存企業からシェアを奪うだけでなく、巨大な新市場を開拓したり、分断された市場を統合した企業を取り上げます。多くの場合、このような機会は、インフラやプラットフォームが成熟した時に生まれ、企業はこれまで不可能だった方法で需要を集約でき、単一の既存企業に取って代わるというよりは、既存の産業を補完したり、市場そのものを劇的に拡大しました。
電信 VS 電話: 通信市場の拡張(1840年代~1900年代)
電信や電話の登場以前、遠距離通信の手段はほぼ存在せず、人々は手紙を使い、数日~数週間かけて意思疎通を行っていたため、メッセージは馬や船よりも速く伝わることはあり得ませんでした。
19世紀半ばにウエスタン・ユニオンなどの企業が構築した電信ネットワークによって、ニュース、個人的なメッセージ、金融情報などが突然、数分で大陸を越えて伝達されるようになります。都市間の商品価格は、電信線で結ばれると収束し、ロイター通信のような通信社も登場しました。
1861年までにアメリカは大陸横断電信を手に入れ、ポニーエクスプレスの郵便サービスは開始からわずか18ヶ月で終了に追い込まれました。国際的には、1866年の最初の大西洋横断ケーブルが設置され、この技術の発明から20年以内に世界的に電信が普及します。年間で8,000万通の電報がやりとりされるまで成長し、市場規模は現在価値で6,000億円規模となりました。
そんな中で、電話はリアルタイムの音声通信を実現することで、電信の訓練が必要で、やり取りが一方通行で、手間・時間・集中力が要るというデメリットを一気に解消し、長距離通信市場を飛躍的に拡張させます。
1876年にグラハム・ベルによって発明された電話は着実に普及し、1880年にはアメリカで5万台以上の電話が使われるようになり、1900年には約135万台が使用されるようになりました。電話会社(ベルの会社で後のAT&T、そして海外でも同等の会社)は、交換機や長距離回線のインフラを整備し、それまでローカルだった通信を全国的なネットワークに集約しました。1920年には年間で約180億分以上の通話が行われ、市場規模は数十兆円規模にまで拡大していきます。

雑貨店 VS 通信販売:販売革命(1890年代~1920年代)
19世紀末、アメリカでは都市と農村の間に大きな購買環境の格差がありました。都市では百貨店や専門店が並び、豊富な品揃えと競争価格が当たり前だった一方、地方の人々は限られた品数と高価格に甘んじるしかありませんでした。こうした市場の分断を打破し、全国規模の消費市場を創出・集約したのが、シアーズ・ローバック社の通信販売モデルです。
シアーズは、数百ページに及ぶ分厚いカタログを全米の家庭に郵送し、誰もが自宅にいながら何千もの商品を選び、注文できる体験を提供しました。この仕組みを支えたのは、急速に整備されていた鉄道貨物網と、1896年に導入された地方無料郵便配達制度です。これにより、都市部と地方の顧客が同じ商品を同じ価格で購入できる環境が整いました。
通信販売の最大の価値は、既存の地元商店の市場シェアを奪うことではなく、それまで可視化されていなかった購買需要を発掘し、1つの企業が広大な国内市場にアクセスできる構造を築いたことにあります。1900年には、シアーズはすでに年間1,000万ドルを超える売上を達成し、当時としては世界最大級のマーチャンダイザーとなりました。
プレハブ住宅や工具、自動車までを扱うそのカタログは、情報の非対称性を解消し、価格競争を全国規模に展開するインフラ的役割を果たしました。こうしてシアーズは、バラバラだった地域市場を1つの統合消費市場へと昇華させたのです。
さらに、物流・在庫・価格体系を自社で一貫して管理したことにより、規模の経済とサービス信頼性を両立しました。顧客にとっては「シアーズで買えば間違いない」というブランド信頼が形成され、農村の個人家庭までもが全国市場の一員になるという前例のない状況が生まれました。
この動きは、単なる小売業の進化ではなく、アメリカにおける“全国規模の消費者社会”の土台を築いた構造転換でした。倉庫の自動化や鉄道による物流革新など、シアーズが築いたプラットフォーム的構造は、100年後のeコマースやアマゾンのロジスティクスモデルにも通じるものです。

手積み方式 VS コンテナ:輸送革命(1950年代~1970年代)
20世紀中盤まで、世界の海運はバラバラの貨物を港で手作業で積み下ろしするブレークバルク方式が主流でした。輸送には大量の人手と時間がかかり、損傷や盗難のリスクも高く、長距離貿易は大企業か国家レベルでなければ手が出せないものでした。そうした状況を根本から覆したのが、1956年にシーランドを創業したマルコム・マクリーンが導入した「コンテナ輸送」でした。彼が打ち出したのは、貨物を規格化された大型コンテナに一括で積み、トラック、鉄道、船を経由して再梱包なしで一気通貫で運ぶというシンプルかつ強力なアイデアでした。「世界初の本格的コンテナ輸送会社」として、1956年に最初のコンテナ船「Ideal-X」がニュージャージーからヒューストンに航行し、史上初の商業コンテナ輸送を行います。
この仕組みによって、積み込みの人件費は劇的に削減され、輸送コストは1トンあたり5.83ドルから0.16ドルへと36分の1になりました。港湾作業の生産性も跳ね上がり、1965年には1人あたり1時間に1.7トンしか扱えなかった荷物が、1970年には30トン以上にまで達しました。これにより、港の回転率が劇的に向上し、輸送にかかる時間と費用が非連続的に下がったことで、以前は貿易に参加できなかった中小企業や新興国の企業も、国際市場にアクセスできるようになったのです。
さらに、1960年代に国際標準化機構(ISO)によってコンテナのサイズが統一されると、港湾設備、クレーン、貨物船、トラック、鉄道が次々と対応を始め、物流インフラそのものがグローバルに接続された巨大なネットワークへと進化しました。このネットワークは「どこからでもどこへでも」商品を運べる土台となり、それまで局所的だった物流と市場を、国境を越えてシームレスに接続しました。また、ベトナム戦争中に米軍がコンテナを採用したことで、その効率性と安全性が実証され、民間への導入が一気に進みました。
結果として、コンテナは単に既存の海運を置き換えたのではなく、まったく新しい市場を開きました。それまで「商品の輸出なんてコストが見合わなくて無理だ」と考えていた企業や国にとって、コンテナはグローバル市場の扉を開く手段となり、世界中の生産地と消費地が初めて一つの巨大な経済圏として結びついたのです。オークランド港や早期に対応した海運会社は繁栄し、対応の遅れた港やばら積み貨物に依存していた企業は競争力を失っていきました。経済学者の中には、コンテナ化こそが20世紀後半の自由貿易協定よりも遥かに世界貿易を促進したとする見方すらあります。
コンテナは世界の距離とコストの壁を取り払い、グローバルな供給網を前提とした産業構造を生み出しました。その影響は単なる物流の改善にとどまらず、今日のグローバリゼーションそのものを形づくる基盤となったのです。1970年代初頭までにシーランドは世界最大級の海運会社となり、グローバル物流における先行者利益を独占。利益率は当時の伝統的海運業の何倍にもなり、「時間とコストの節約=市場シェアの拡大」という構造を先んじて取り込んだ成功例です。

産業革新の共通要因「過去から学ぶ未来のヒント」
蒸気機関車からスマートフォンまで、過去200年のイノベーションの歴史には、ある共通した実現要因が見られます。それらは単なる技術の優劣ではなく、市場構造を抜本的に再定義する「仕組みの変革」を伴っていました。以下では、それらの要因と、現代の起業家がそこから何を学ぶべきかを整理してみたいと思います。
■ 技術革新
どの産業変革も、既存手段と比較して圧倒的な性能・コスト改善が見られました。自動車は馬より速く清潔で、電灯はガス灯より明るく安全でした。電話は世界初のリアルタイム音声通信を、コンテナ輸送はコストを36分の1にしました。このような技術革新による新たな価値提案によって、既存プレイヤーを凌駕しました。
■ インフラとネットワークの活用
変革の中心となった企業は、鉄道や送電網、通信インフラの活用に長けていました。場合によっては政府の支援も受けながら、インフラの整備がイノベーションを加速させました。シアーズは郵便鉄道網を活用し、自動車は道路インフラの整備とともに競争力を築きました。
■ 標準化とプラットフォーム化
ISO規格のコンテナ、IBMのSystem/360など、標準化は市場を均質化し、ネットワーク効果を促進しました。また、電話のように、参加者が増えるほど価値が増す構造が支配を加速させました。
■ 規模の経済と流通の優位性
組立ラインを確立したフォードや、巨大倉庫とラストマイル配送網を構築したアマゾンのようにスケールによってコストを引き下げ、他社が真似できない優位性を築きました。製品だけでなく、効率的な流通戦略の設計が変革の核心にありました。
■ タイミング:社会的文脈とエコシステムの整合
産業変革は、技術革新と社会の「準備」が整ったタイミングで瞬時に普及しました。自動車は都市の衛生問題と大量生産の実現タイミングに合致し、スマートフォンはワイヤレス通信とチップ性能の進化に支えられました。
■ 先見的なリーダーシップと大胆な実行力
偉大なビジネスほど、初期にはトレードオフが存在します。フォードやベゾスのように、初期利益を犠牲にしてでもスケーリングに賭ける経営者が、新市場の覇権を握りました。巨額の資本投下と迅速な意思決定が、同じ技術を持つ他社と決定的な差を生みました。
■ 「スピード」がイノベーションに最重要
馬から車への移行は15年以内、スマートフォンの普及も10年以下。一方で、ガス灯から電灯、電話の普及には数十年を要しました。汎用技術の普及速度は時代とともにどんどん加速しており、現代のAIなどの新技術も数年単位でパラダイムを変える可能性があります。
つまり、起業家が意識すべきことは以下の通りです:
-
真に顧客体験を革新することに集中する
-
技術だけでなく、インフラと流通網が整っているか時機が重要である
-
標準化・ネットワーク効果などを意識し、構造的な優位性を築くこと
-
規模の経済と社会文脈(規制、倫理など)を考慮すること
-
速く、長期思考で、将来から逆算した初期のトレードオフを取りに行くこと
結論として、旧来型の企業を直接置き換えるにせよ、新たな巨大市場を切り拓くにせよ、産業革命から現代のデジタル経済に至るまで、一貫したパターンが存在しています。技術革新とインフラや規制が整備されたタイミングにおける、競合を凌駕する実行力の組み合わせは、常にビジネスの歴史で産業変革を起こしてきました。
パラダイムシフトは、誰もが予想するよりも早く訪れます。21世紀においても、このパターンは今後も続く、あるいはさらに加速すると予想されます。AIや再生可能エネルギーなどの分野においても、同様のケーススタディが語られるようになるでしょう。
過去200年にわたる市場の変遷は、変革に成功した企業やリーダーに共通する示唆を与えてくれます。あらゆる時代において勝者となった人々とは、その時代の顧客が価値を享受可能なテクノロジーを見極め、それを活かすために果敢に動き、独自の条件で市場を再構築した人々でした。
もし現代で産業変革するビジネスアイデアは、例えばこんなものが考えられるかもしれません。
労働集約型の特定業界向けAIやロボティクス
-
技術革新 画像認識や自然言語処理といったAIの汎用化、ロボットアーム・自律走行搬送ロボットなどの進化により、人間の代替を超えた「高度作業」や「24時間労働」が可能になる。
-
インフラとネットワークの活用 5G/6Gなどの超高速通信インフラや、産業用IoTプラットフォームが徐々に勃興してきている。政府や業界団体がネットワーク標準を整備すれば、一気に普及が加速しやすい。
-
標準化とプラットフォーム化 製造ロボットやAIアルゴリズムのインターフェースを標準化し、「すぐに追加・アップデートが可能」な“ロボティクスOS”が広がると、NVIDIAのような特手の事業者が統合プラットフォームを牛耳る可能性が高い(例:AndroidがスマホOSをほぼ独占したように)。。
-
規模の経済と流通の優位性 大規模な無人工場や無人コールセンターなどを運営するプレイヤーが、生産コストを極限まで下げつつグローバルに製品を供給する。Amazonが物流を制したように、AI+ロボットによる特定のサービス提供を制した企業が特定産業全体のインフラになり得る。
-
タイミング:社会的文脈とエコシステム 労働人口減少や生産コスト高騰が進む国・地域ほど、AIやロボティクスへの転換メリットが大きい。労働力不足への対策という社会要請が強まれば、一気に普及が進む。
新たな事業アイデアや起業構想を練りたい方、ぜひお気軽にご連絡ください
まだ曖昧なアイデアであっても、共に検証し、突破口を探っていくことに情熱を注いでいます。起業家の方や起業を検討中の方と共に、ビジネスの磨き込みから資金調達戦略まで幅広くサポートいたしますので、新しい挑戦に向けて、一緒に踏み出しましょう
詳しい活動は、以下のリンクからご覧いただけます:
すでに登録済みの方は こちら