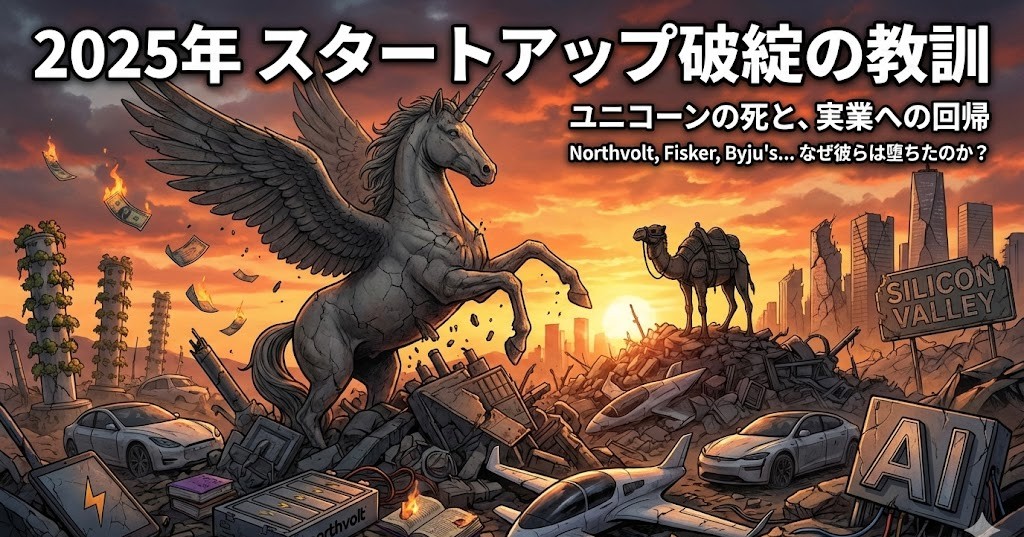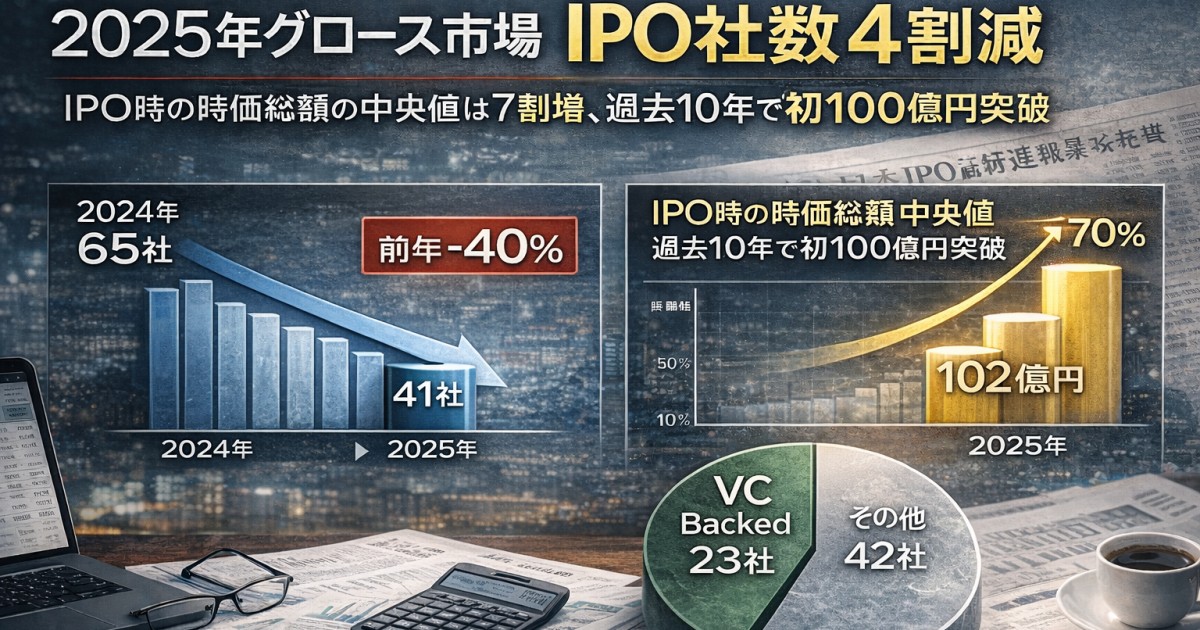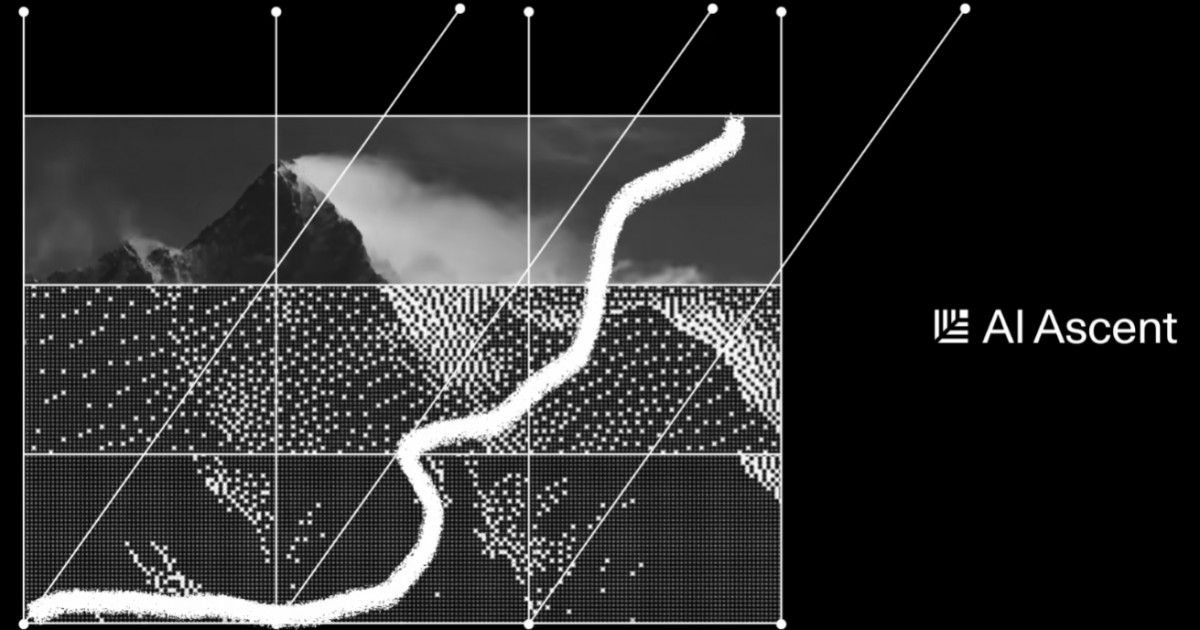米国でも多い「初期黒字経営」後、VC調達するスタートアップの成長戦略
-
はじめに:米国スタートアップ全てが赤字Jカーブ戦略ではない
-
Zoominの創業:PMFまで、VC調達しない決断
-
ブートストラップの強さ:顧客思考と利益志向
-
転換点:黒字経営から、なぜVC調達へ?
-
更なる飛躍の鍵:大手との事業連携とAIの進化
-
まとめ:スモビジとスタートアップという二項対立ではない
1. はじめに:米国スタートアップ全てが赤字Jカーブ戦略ではない
スタートアップと聞くと、多額の先行投資による赤字を抱えながらでも、とにかく売上の急成長を狙うためにVC(ベンチャーキャピタル)から多額の資金を調達するというイメージが強いかもしれません。ですが、
実はアメリカにも黒字や少額の自己資金(いわゆるブートストラップ)で成長しているスタートアップが数多く存在します。
特にSaaSやBtoB領域では、まずは目の前の顧客に価値を届けることに集中し、しっかり利益を出して黒字経営してから初めてスケールを考え、成長を加速させるためにVCなどから株式による資金調達を行う事例も珍しくありません。
今回はそんな事例の一つとしてZoomin(イスラエル発のSaaS企業)がたどった道のりを紹介します。同社は当初資金調達をせずに収益をあげながら顧客を獲得し、その後、さらなる成長戦略のためにVC(Bessemer Venture Partnersなど)から出資を受け、最終的にはSalesforceによる買収という大きなエグジットに結びつけました。
このストーリーを追うことで、「黒字運営ができている企業でもなぜVC調達が必要になるのか」「黒字経営のメリットと限界は何か」という点と同時に、アメリカを含むグローバルなスタートアップシーンでは、むしろ“最初は資金調達ナシ→スケール時にVC調達”という流れが十分主流な選択肢であるということです。
2. Zoominの創業:PMFまで、VC調達しない決断
「ナレッジ・オーケストレーション」という新市場
Zoominは、CEOのGal Oron(ギャル・オロン)、Hannan Saltzman、Joe Gelbの3名が共同創業した企業です。彼らが見つけたのは「企業内に無数に散らばっている製品マニュアル、社内資料などを統合管理し、ユーザーが必要なときに瞬時に探し出せるようにする」という大きな課題でした。
製品マニュアルがSharePoint、Confluence、Google Driveなどに分散しているため、複数の場所を行き来しなければならないという不便さです。
この問題はどの大企業も抱えるホリゾンタルな巨大課題であり、ここにイノベーションの余地があると確信した3人は、当初はVCからの資金を入れず、自己資金だけ(ブートストラップ)で事業を開始します。
なぜブートストラップの道を選んだのか
スタートアップであれば、シード段階ですぐにエンジェル投資家やVCにアプローチする選択肢もあります。しかしZoominの場合は「まずは真に顧客の問題を解決するプロダクトを創ってお金を掛けずとも販売できるかどうか、そこから得た収益だけで運営できてユニットエコノミクスが証明できるかどうかの両方が揃ってはじめて、真に急成長のアクセルを踏んでも良い領域かどうか判断可能になる」という発想で動きました。
その結果、サービス投入当初は大規模なマーケティングや豪華なウェブサイトなどは用意できません。いわゆる「イケてるスタートアップ感」は一切なかったそうですが、初期顧客に真摯に対応することで、使ってもらいながら改善していく地道なプロセスに全力を注いだのです。
創業初期は、スケールしない“地道”な成長を目指す
こうした地道な努力の成果が実を結び、一般的なスタートアップよりは遅い歩みだとしても、ServiceNowやMcAfee、Dell EMCなど、業界を代表する大手企業を含む20~30社の顧客を徐々に獲得していきました。エンタープライズ向けSaaSの場合、1社あたりの契約額が大きいうえ、成功事例が増えると口コミや紹介で自然に広がりやすい構造を持っています。結果、Zoominは外部からの潤沢な資金がなくとも黒字経営でやりくりができるようになったのです。
一方で、逆に社内では「マーケティングや採用、R&Dなどをもっと加速させて先行投資すれば、はるかに大きな市場を獲得できる」という確信が高まっていました。そこで彼らは、あえてリスクを取ってVC調達を検討することになります。
3. ブートストラップの強さ:顧客思考と利益志向
ブートストラップの「利点」
ブートストラップには、以下のようなメリットがあります。
-
資金調達にとらわれない“顧客優先”の姿勢
初期のPMF前に外部投資家から資金調達すると、早期のうちからトップラインの売上数値を過度に追いかけたり、何かにお金を使わなきゃと「お金を使う前提」の誘惑が生まれます。一方、限られたキャッシュで動くZoominは、なにより顧客を満足させることが売上の源泉であるため、自然と“顧客の問題解決こそ最優先”の文化が強化されました。 -
堅実な収益モデル確立
赤字前提で拡大路線を突き進むのではなく、まずは事業単体でキャッシュフローを回すことを重視するため、“収益モデル”が早期に洗練されました。これにより、明確なグロースドライバーや赤字倒産リスクが限りなく低いため、投資家側もより魅力を感じ資金調達が即完了しました。 -
経営のコントロールと柔軟性
ブートストラップの段階では、創業者たちは“どこに注力すべきか”を自分たちだけで意思決定できるため、製品開発の優先順位を“顧客満足”に総動員できます。
ブートストラップゆえの「課題」
ただし、ブートストラップも万能ではありません。人材採用も、売上やキャッシュフローを見ながら徐々にしか拡大できず、競争が激化している市場だと攻めきれずに競合他社に追い抜かれる恐れもあります。黒字を維持しているとはいえ、さらなる大きなチャンスを目前にしたときに“先行投資”ができないというジレンマです。
実際、Zoominは大手顧客を順調に獲得したものの、「ここで加速すれば一気に市場を独占出来る」というタイミングで自己資金の不足を痛感し、VC調達へと踏み出す決断を下しました。
実は、これは米国ではよくあるシナリオで、最初の数年間は自己資金で黒字で回しながらプロダクトを磨き、確実に黒字化させて成長へのボトルネックが明確になり、それが資金によって加速できると確信した段階でVCに“成長のガソリン”を注入してもらうのです。
Accelという米国の名門VCもグロースファンドを組成した目的は、実はこういった黒字経営だが、成長資金があれば急加速して成長できるポテンシャルのある企業に投資する目的であると明言しています。
4. 転換点:黒字経営から、なぜVC調達へ?
Zoominの成長可能性を見抜いたBessemer
ZoominがVC調達に動き出した際、当時は「ウェブサイトは洗練されていない」「Go-to-Market戦略が明確ではない」「リーダーシップチームも小規模」と、一見“魅力が薄い地味な企業”に見えたそうです。実際、派手なピッチやPRはありません。
それにもかかわらず、大手VCのBessemer Venture Partners(以下Bessemer)がZoominに強い興味を示した理由は、「顧客が猛烈なファンになっていた」という点にありました。デューデリジェンスの過程で顧客企業にヒアリングをすると、ほとんどの顧客が「Zoominはただのベンダーではない、最高のパートナーだ」と絶賛していたのです。さらに、サービスがもたらす価値(顧客サポートコスト削減、ドキュメント管理の効率化など)の実績が明確でした。
「黒字」なのに、株式で「資金調達」する価値
ここで改めて問いたいのは、アメリカでは実は多い「黒字で自走できるのに、そのタイミングでなぜVCから資金調達するのか?」ということです。Zoominの場合、その答えは大きく2つあります。
-
自社の競争優位性を強化する“人材投資”
Zoominの場合、PMFが完了していましたが、より自社のプロダクトやサービスの品質を他の追随を許さないレベルに向上させつつ、大企業顧客をさらに増やし、国際展開や協業先の拡大を加速するには、優秀な営業チーム、カスタマーサクセス体制、さらに高度なエンジニアリングが必要でした。ブートストラップだけでは、採用と育成に先行投資できず、時間がかかりすぎる課題があります。一気に成長速度を上げるため、返済の必要のない外部資金を調達しました。 -
市場シェアを急拡大させる“マーケティング投資”
Zoominが目指すのは単なるサポートツールではなく、「ナレッジ・オーケストレーション」という新たな市場を独占することです。これを業界に広め、その市場の圧倒的な第一想起を取り続けるためには、カンファレンスへの出展や企業との共同プロモーションなど、本格的なマーケティング活動が必要です。自社だけで黒字を確保しながら進めていたのでは、インパクトを出すまでに長い年月がかかります。外部資金を活用すれば、タイミングを逃さず、一気に市場シェアを急速に獲得できます。
Zoominはこの二つの理由を軸に、Bessemerとのパートナーシップを組みました。自社がすでに得ていた“利益志向”に、VCの資金とネットワークが掛け合わされることで、成長スピードは格段にアップしました。
5. 更なる飛躍の鍵:大手との事業連携とAIの進化
顧客こそが、最強の営業マン
ブートストラップ時代に培った「売上よりも粗利や顧客のリピート率を意識する」「顧客の課題に真摯に向き合う」という姿勢そのものは、資金調達後も変わりませんでした。その結果、顧客がZoominの“最大の宣伝マン”となり、業界カンファレンスなどで積極的に紹介してくれる流れが生まれていました。
大企業とのパートナーシップを成功させるリスクとリターン
さらに、Salesforceなどの大企業とのパートナーシップが急速な成長を実現する大きな推進力となりました。大企業と組むことは、リソースや顧客基盤を一気に拡大できるチャンスがある一方、相手企業の都合に振り回されるリスクもあります。Zoominはこの点、Salesforce側に自社専属チームを設けて本業と分離してもらい、スタートアップの武器である迅速性を維持したまま、大企業のリソースを活用する戦略をとりました。
Salesforce内部で「顧客企業が抱える無数のドキュメントをZoominが統合・可視化する」という事例が増えていき、さらにAIブームの到来とともに「未構造化データこそがAIが最も価値を発揮できる」という認識が高まったことで、Zoominの存在感は一気に高まりました。
Salesforceに買収される
2023年にChatGPTなどLLM(大規模言語モデル)が注目を浴びはじめると、Zoominの経営陣はすぐに機能開発とマーケティングメッセージを“AI連携”にシフトします。既存のナレッジ管理機能を「高品質データをAIに食わせるための整理されたデータ」と位置づけることで、企業価値を一段と引き上げました。
こういった波と、Salesforce内での評価が、最終的に2024年のSalesforceからの買収へと結びつきます。ブートストラップから黒字を維持しながら着実に伸ばし、成長期にVC資金を得て一気に拡大し、最終的に大手企業に買収される。日本では、アメリカのスタートアップは全て初期から巨額の先行投資で赤字のJカーブから成長しているみたいな認知が多いですが、意外と米国スタートアップではこういったケースは多かったりします。
6. まとめ:スモビジとスタートアップという二項対立ではない
Zoominの事例は「ブートストラップで黒字を出せるならVC調達は不要では?」という問いに明確な答えを与えてくれます。“本当に必要なタイミング”、つまり先行投資すればより成長を加速できると確信できた時にVC調達は大きな価値を発揮します。
最後に補足したい重要な視点として、ブートストラップ、黒字経営からのVC調達はZoominのようなテック企業やSaaSスタートアップに限った話ではありません。
日本では「スモールビジネス(スモビジ)とスタートアップは別物」という二項対立の議論が目立ちますが、実際のところ“成長を目指す企業”という点において両者は地続きです。
コンサルティングやBPO、受託開発などの「スモビジ」と謎に一括りにされてしまいやすいビジネスモデルでも、独自の強み・ノウハウがあれば、成長を一気に加速するために人材に先行投資をするための資金調達(場合によってはVC資金も含む)を検討することは十分にあり得ると思います。
例えば、コンサル領域でいえばベイカレント・コンサルティングは、上場当時の時価総額325億円から今や5,000億円超という大規模に成長を遂げました。SHIFTも36億円の時価総額から3,000億円まで成長を遂げています。
だからこそ「初期に黒字化しやすいからスモールビジネス」「初期に赤字を掘るモデルだからスタートアップ」という二元論はあまりに短絡的だといえます。

そして、実は米国のスタートアップも必ずしも赤字を掘る「Jカーブ」ではないという事実です。アメリカでもブートストラップで黒字を維持しながら粘り強く成長し、あるタイミングでVCから資金を入れて一気に大きくなる企業は意外と多いです。オンラインビデオツールのZoomも最初のVCからの外部調達時点で既に黒字でした。Zoominのように「まず収益基盤を固めてから、満を持してVC調達をする」例も決して珍しくありません。
最終的に大事なのは、自社がどこを目指し、そのためにどのような成長戦略を描くのかという点です。黒字経営から一段上の、市場を牽引する企業への飛躍を目指す際、VC調達という選択肢は有力な選択肢になり得るはずです。
スタートアップの世界には無数のパターンがありますが、結局は「自分たちが持続的に勝てる市場で、しっかりと価値を高め続けられるか、キャッシュフローを生み出し続けられるか」という問いに尽きると思います。そのうえで外部資金をどう活用するかを考えることこそ、起業家にもVCにとっても長期的な成功の鍵となるのではないでしょうか。
新たな事業アイデアや起業構想を練りたい方、ぜひお気軽にご連絡ください
まだ曖昧なアイデアであっても、共に検証し、突破口を探っていくことに情熱を注いでいます。起業家の方や起業を検討中の方と共に、ビジネスの磨き込みから資金調達戦略まで幅広くサポートいたしますので、新しい挑戦に向けて、一緒に踏み出しましょう
詳しい活動は、以下のリンクからご覧いただけます:
すでに登録済みの方は こちら