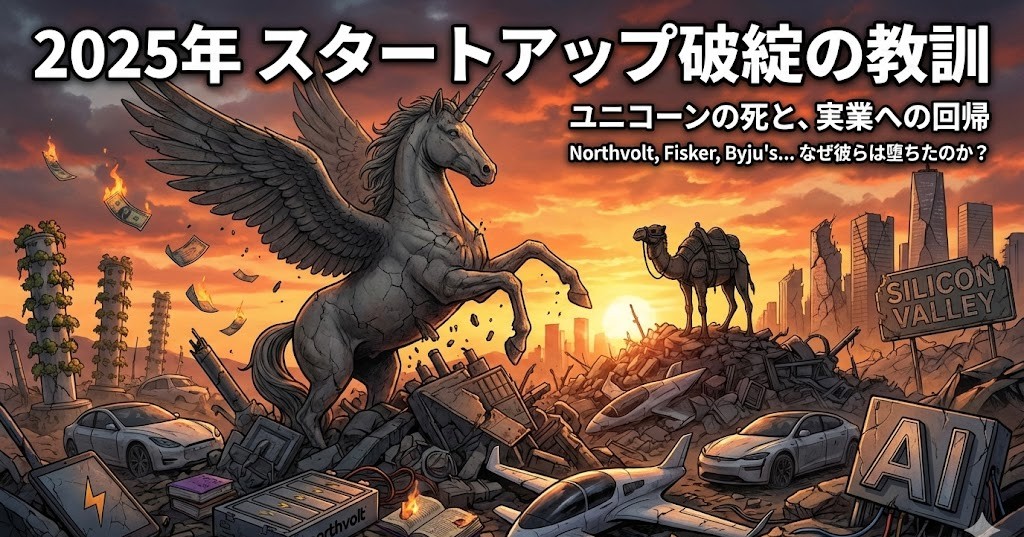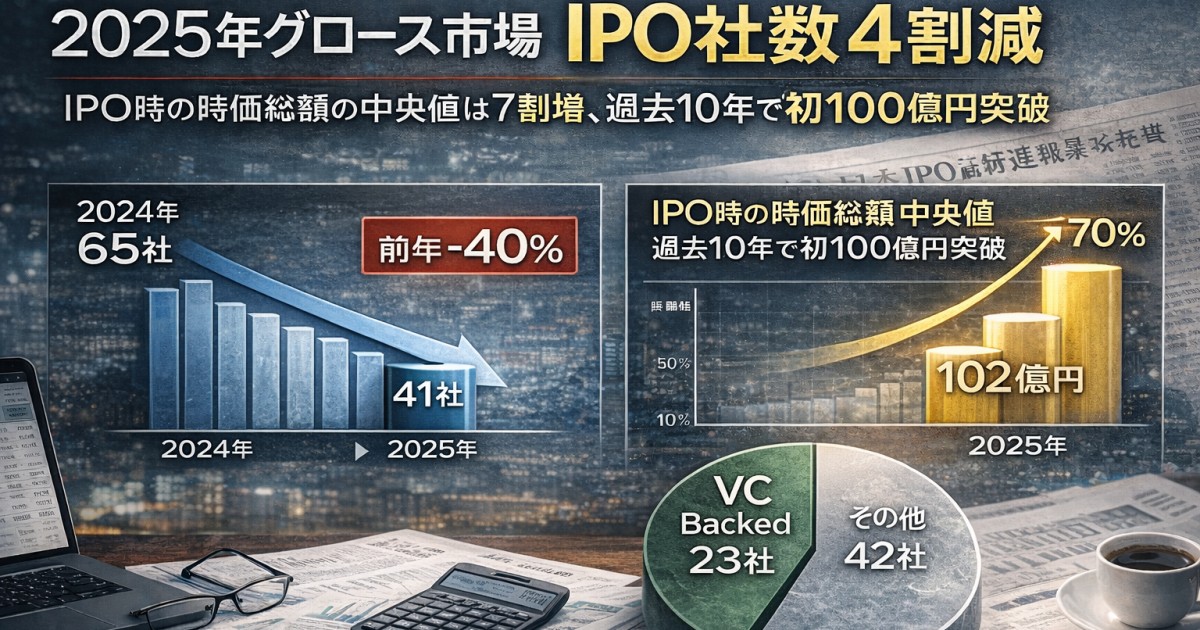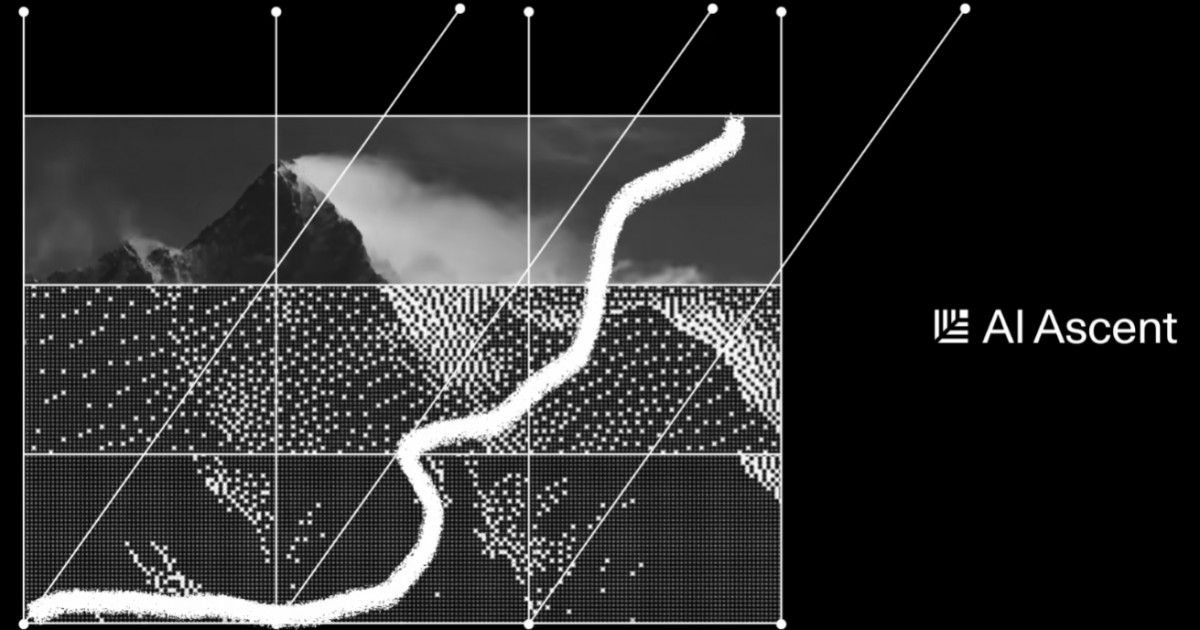PMF戦略 ~市場とタイミングを見極める~
「顧客探索から始めてはいけない理由」

【要約】
1. PMF以前に「市場選定」が最も重要な意思決定である
PMFはプロダクトとマーケットの適合だが、世の中の記事の多くはプロダクトの議論が中心であり「市場」という要素は若干過小評価されている。
2. スタートアップの失敗の多くは「市場がなかった」ことによる
チーム、プロダクト、戦略が優れていても、市場がなければPMFは不可能。逆に、優れた市場であればプロダクトが未完成でも受け入れられる。
3. 市場参入のタイミングが市場の優劣と事業の成否に大きく影響する
市場が「存在しない」とは、永遠にないのではなく「まだ早すぎた」可能性が高い。市場の波が来る前に体力を使い果たしてしまうことがスタートアップの失敗の本質であることが多い。
4. 過去の失敗に未来の成功のヒントが眠っている
General MagicやWebvanのように、同じアイデアでもタイミング(外部環境)の違いで成否が分かれる。過去の失敗を徹底分析することで、成功への道が見える。
5. 外部環境(技術、規制、消費者行動)の変化を起点に市場を見極める
市場機会は、テクノロジーの進化、消費者心理の変化、法制度の整備などによって初めて開花する。つまり、環境の波を読む力が市場選定には不可欠。
6. 「顧客課題」探索だけでは未来の成長市場を見抜けない
今の顧客のニーズを調べるだけでは不十分。将来その課題を持つ人が増えるか、そのニーズそのものが大きくなるかという仮説を持つことが重要。
7. "完全に新しいアイデア"は存在しない。
重要なのは"なぜ今か"新しいように見える成功事例も過去の失敗の延長線上にある。重要なのは「なぜ今ならこのアイデアが機能するのか」を論理的に説明できること。
1. 「市場」の選定が最重要である
1)PMFを阻む最大要因=市場が存在しない
PMF(プロダクト・マーケット・フィット)と聞くと、多くの方が「プロダクト開発戦略」や具体的な「Go to Market戦略」などのプロダクトや事業戦略の話を思い浮かべるのではないでしょうか?
PMFに関する記事は「市場選定後の起業家の方」向けに書かれていることが多く、顧客課題の見つけ方、顧客へのインタビュー方法、バリュープロポジションの作り方や差別化戦略、PMFの測り方、営業や製品開発戦略など、PMFに向けて「顧客」にどう「プロダクト」を適合させていくかという内容が大半です。
もちろんこれらは大変重要ですが、そもそもPMFとは、製品(Product)と市場(Market)の適合のことであり、製品の前にそもそもどの市場で挑戦するかが非常に重要な要素だと思います。にもかかわらずPMF関連の記事の多くは、
「既に優れた市場(マーケット)が実在する」前提で書かれている
と感じています。
一方で、多くのスタートアップがPMFできずに事業継続を断念していく最大の理由は、プロダクトの問題ではなく、そもそも充分な「市場が存在しなかったから」という事実です。
2)プロダクトより重要な「市場」選定

https://sairu.co.jp/method/15076/
上記のグラフを拝見されたことがある方は多いと思いますが、
あえてここで強調したいのは、スタートアップの撤退理由が、優れたプロダクトを創れなかったわけでも、ビジネスモデルを間違えたわけでも、顧客の声を聞かなかったわけでも、チームが適切でなかったわけでも、競合との競争に負けたわけでも、価格戦略の失敗でもなかったわけであり、
プロダクトや戦術の工夫の余地なく「市場が存在しなかった」という事実です。
(市場が存在するのであれば、プロダクトの機能を開発し直したり、To CからTo Bにピボットしたり、工夫しつづけてPMFを目指すだけです)
2番目に多い失敗理由とされる「資金が枯渇した」も、別の角度から見ると「市場がなく売上が上がらない→追加調達が難航する→資金が底を突く」という流れであり、やはり「市場がなかった」可能性が高いです。当たり前ですが、市場がない状態では、どれだけ優秀なチームがいて、プロダクト開発を頑張ったとしても、いずれ資金が尽きて終わりということです。
市場について、サーフィンのアナロジーで考えてみるとわかりやすいです。

波(市場)がなければ、プロサーファー(優れた起業家)もサーフィン(PMF)しようがない。逆に、波(市場)があれば、優れていなくてもサーフィン(PMF)できる可能性もある。
どんな優れたチーム(プロサーファー)も波のない海(市場がない場合)では、サーフィン(PMF)することができません。逆に波さえあれば、プロサーファー以外でもPMFできるチャンスが存在するということです。
どんなサーファー(起業家)であれ、他のサーファー(競合)が少ないが、優れた波が来る海(将来成長する市場)を選ぶことは重要です。
バスケの神様、マイケルジョーダンは最高の「人」です。その彼も全盛期に2年間ほどMLBという「野球」市場に挑戦しましたが、成功を収めていません。NBAの「バスケ」市場だからこそ、神様になれたのです。(Founder Market Fitの話も少し含まれていますが、この話はまたどこかで)
もちろんプロダクトの完成度や実行力はとても重要です。「事業を成功させるために何が重要か」と問われれば、創業チームの実行力や技術力、営業やマーケティング、資金調達力、人脈ネットワークなど、当然にして重要な要素はたくさんあると思います。私も創業チーム=「人」はとても重要だと考えています。
でも「市場」に勝つことはできません。
「市場」に関して、米国で最も尊敬される名門ベンチャーキャピタルの1社であるBenchmarkのAndy Rachleffは、以下のように語っています。
When a great team meets a lousy market, market wins.
When a lousy team meets a great market, market wins.
When a great team meets a great market, something special happens.
素晴らしいチームとひどい市場が出会うと、市場が勝る
ひどいチームと素晴らしい市場が出会うと、市場が勝る
素晴らしいチームと素晴らしい市場が出会うと、凄い事が起きる
「市場」という要素が、チームやプロダクトという要素に勝るほどの影響力を持っており、「優れた市場」を選ぶことの重要性を語っています。
市場がない状態なら、たとえ素晴らしいチームでも成功は難しく、逆に急速に成長している優れた市場であれば、あまり洗練されていないプロダクトやサービスでも顧客が受け入れ、売上が立ち始めるという一面もあります。
違う言い方をすれば、洗練されていないプロダクトでも売れていくような、今まさに勃興し始めている市場を見つけよということになります。
YoutubeもUberも、AirBnBも、iPhoneだって初期から完璧なプロダクトではなかったわけですが、市場が既に優れていた、または自らが市場成長のボトルネックを解消し、爆発的に市場を成長させる起爆剤となったため、成功したわけです。
PMFについては最初から「プロダクト」中心の議論となってしまいがちですが、いま一度、顧客課題の探索やプロダクト以前に「市場が今後伸びるのか」を俯瞰して検討することが大事です。
3)顧客課題の探索から始めてはダメな理由
こちらも米国で有名なa16z創業者のMarc Andreessenの有名な言葉です。

Market is the most important factor in a startup’s success or failure.
市場はスタートアップが成功するか、失敗するかの最重要要因である
これまで「市場」が失敗の要因であるという話をしてきましたが、逆に言えば、「市場」こそ事業成功の最重要要因であるという事です。
まず、市場が優れていないとは具体的にはどういうことか?
それは事業開始後に想定よりも
-
顧客候補「数」が増えなかった(or 減少してしまった)
-
顧客「単価」が上がらなかった(or 減少してしまった)
ということです。でもここで一つ疑問が湧きます。
多くの起業家の方は、事業開始前に必ず顧客にインタビューしているはずですし、しっかり課題の有無などを把握してスタートしているはずです。にもかかわらず、なぜ充分ではない、優れていない市場に挑戦してしまうのか、その答えは「今現在の顧客」のことを考えすぎているからだと思います。
もし急速に成長する事業を立ち上げたい場合は、「今現在の顧客」ではなく、「未来の市場機会(潜在顧客)」を捉えることが極めて重要です。
成功した起業家の方々は、結果的にある程度優れた市場で起業したから成功しているわけですが、今世の中で語られている起業家の方の創業期を読むと、まず顧客課題の探索から始めていることが多かったりします。
顧客候補の課題を探索している時点で「市場を既に選択」しています。
それでも成功できているのは、最初に選んだ顧客のいる市場が優れていたというケースが少なくないからであり、その結果「市場選定」については語られることが少ないです。(過去の物語は常に偶然性が低く見える)
そもそも、今現在の顧客の課題の深さを測ることと、市場が優れているか(その課題を抱える顧客が増加するか?その課題自体の大きさが拡大するか?)について考えることは、根本的に異なる視点です。
課題を測ることは、その特定の問題に顧客がどれくらいの影響を受けているのか、またはそれがどれだけ深刻であるのかを把握するために大事です。しかし、今後のテクノロジーの進化や社会的な変化による顧客層の拡大や課題の進行を予測することが未来の市場機会を捉える上でより重要となります。したがって、今の顧客が抱える課題がどれだけ深刻かを理解するだけでなく、その課題がどれくらい拡大し、進化していくのかの仮説を立てることが戦略的に非常に重要です。
つまり、現時点ではまだ課題や欲望を深く感じていない、あるいは少数の人しか抱えていないが、「将来的にはその欲望や課題を抱える人が増え、さらにそれ自体が肥大化する、頻度が増えると思える市場」=優れた市場で製品やサービスを提供することが鍵となります。
また、そもそもほとんどの顧客は自身で課題を認識していません
(PayPayを開始する前はQRコード決済に対しての市場調査では99人が「そんなものはいらない」と言った)
上記の理由から、急成長事業を成功させた事例において、事業開始前に真に市場選定の重要性を理解して開始した事例は実は多くないため、市場選定の重要性に関しては成功者の認知ギャップが存在しています。
過去にいわゆるスモビジの1社目を起業した時、スタートアップ的起業を志してVCと壁打ちしていた時期を振り返ると、市場の重要性を理解できておらず、とにかく顧客インタビューから始めて疲弊していました。2022年にVC業界に入り、ベンチャーキャピタリストという仕事を通じてたくさんの事例に触れて、この「市場」を選定する重要性を痛感できました。
だからこそ、これから早く大きく成長する事業を創ることを志向する方々に対して、優れた市場を選定する重要性を強くお伝えしたいと思い、このブログを書いています。
では、どうやって「優れた市場」を見極めればよいのか?
もう少し深ぼっていきます。
2.市場の優劣は「タイミング」が決める
1)タイミングによって市場の優劣は変わる
何度もお伝えしたとおり「どの市場で事業を始めるか」を決断することは、スタートアップ起業家や創業チームの方々にとって、最も重要な意思決定であると考えています。
そもそも、市場を考える上で重要なことは、市場は外部環境の変化に伴い、刻一刻と変化してしまうということです。どの時間軸でとらえるかによって、市場の優劣は大きく変化するという事です。
なぜ、これだけPMFに関する記事やブログ、知見が広まっているのにも関わらず、多くのスタートアップの優秀な起業家たちが、優れた市場ではなく、存在していない市場に挑戦してしまうのでしょうか?
その理由の1つは
市場に参入する「タイミング」を誤ってしまうから
ではないかなと考えています。「市場が存在しない」ということと、市場参入のタイミングがどう関係するのか?再度サーフィンで例えます。

左:波が来る前にパドリングしすぎて、波が来る前に疲れ切ってしまう。真ん中:波が全くない海で、サーフィンしようがない。右:良い波に乗る準備が出来ておらず、他の人が良い波でサーフィンしている
サーフィンで波に乗るために重要なのは、大きな波が来ると予測される適切な位置にポジショニングし、適切な向きとタイミングでパドリングを開始することです。
つまり「市場が存在しない」とは本当に市場が存在していない場合に加え
Too Early:市場参入が早すぎて市場が勃興するまで体力が持たなかった
場合があると思います。
つまり、「今」はまだその市場は存在していないだけであって、外部環境の変化や時間の経過で市場が勃興する可能性を秘めています。あくまで「その時点では」市場が存在していなかったということです。成長資金を外部調達して急成長を目指す企業を志向する場合、資金や時間にリミットがあるため、この「タイミング」という要素は非常に重要です。永遠にパドリングはできないので、波が来る前に力尽きてしまいます。
1番右の画像のToo Lateは失敗分類でいうと、参入が遅すぎて競争に負けたという分類ですが、あくまで私の意見では、優秀な起業家の方ほど、本当に市場がない、あるいは市場参入が遅いというケースは少ない気がしています。
理由は優秀な起業家であればあるほどその事業領域に誰よりも精通していますし、技術や流行トレンドなどにおいても世の中の大多数の人よりも遥かに先進的な考えやマインドセットを持っている可能性が高いからです。
その結果、自身がリスクテイカーかつアーリーアダプターすぎて、起業家の方にとっては最適なタイミングだと思っても早すぎてしまう、技術革新が世の中の人が受け入れるレベルには到達していない、あるいは顧客となるであろう世の中の大多数の人たちが心理的に受け入れる準備ができていない段階で参入して資金が底をつき、撤退を余儀なくされているいったことが起きてしまうのだと思います。
これについてもa16z創業者のMarc Andreessenが語っています。
My experience is the great founders almost always feel like they’re too late, and you’re almost always too early.We almost never see a qualified founder fail because they were too late to market. It’s almost always because they’re too early to market.
If what you’re working on was the hot thing 3-4 years ago, you’re probably right on time because the infrastructure and consumer behavior has now caught up.
私の経験では偉大な起業家は常に遅すぎると感じているが、ほかの人々は早すぎると考えている。優秀な起業家で、市場参入が遅すぎて失敗することはほとんどない。ほとんどが市場参入が早すぎて失敗している。
起業家のあなたが今取り組んでいるものが、3~4年前に世の中でホットトピックになった物事であれば、おそらく正しい市場参入タイミングだ。インフラ(技術革新)や消費者(顧客)の行動がようやく整ったのが今だろう。
市場参入タイミングの重要性と多くの起業家が事業参入が早すぎてしまいやすいということは理解いただけたかと思います。以下でもスタートアップの成功において、事業開始のタイミングが重要な成功要因であることが示されています。

次は市場への参入が早すぎて失敗した具体的な事例を紹介します。
2)技術障壁が阻んだiPhoneと偉大なチーム
1990年代初頭にAppleからスピンアウトしたGeneral Magicという企業をご存じでしょうか?(ドキュメンタリー映画にもなってます)

General Magicの構想
iPhoneが2007年に誕生する15年前に、アプリケーション、タッチ操作、接続機能を備えた「ポケットコンピュータ」に相当するもタッチパネルのスマートフォンの開発に挑戦した企業です。
今と比べると初代iPhoneでも使い勝手がひどいことを考えると、相当使えない気がしますよね。失敗した理由は、挑戦が「早すぎた」からです。ではなぜ早すぎたのか?それは
-
モバイルネットワークは遅く、不安定だった
-
バッテリー技術は不十分ですぐに充電切れした
-
製造コストが低くできず、販売価格が高すぎた
-
通信インフラも黎明期で通信費用も高額だった
-
多くの人が日常生活でデジタル機器を持ち歩く習慣がなかった
彼らは素晴らしい技術力を保有するチーム(後に「iPodの父」として知られるトニー・ファデル氏を含む)だったにもかかわらず、この製品は失敗に終わりました。初代iPhoneよりも遥かに体験価値が低いにもかかわらず、価格は初代iPhoneの2倍以上で1,000ドル以上したため、この時点では買おうとする顧客はいなかった、つまり、「市場が存在しなかった」わけです

2007年に登場したAppleのiPhoneは大成功を収めますが、上記の通り、General MagicとiPhoneでは外部環境の状況が大きく異なります。その理由は、明確な外部環境の変化=「波」を捉えることができたからです。その波とは簡潔にまとめれば、以下の通りです。
-
ネットワークインフラ
2007年頃には、より高度なウェブブラウジングやアプリケーションをサポートするのに十分な速度(3G)の携帯電話ネットワークが整備されていました。1990年代には、データ速度は遅すぎ、Wi-Fiはまだ普及していませんでした。 -
ハードウェア
2000年代半ばには、タッチスクリーンは1990年代初頭と比較して、遥かに反応が良く、製造コストも低くなっていました。また、バッテリーの効率が改善され、毎日の充電がより現実的になりました。 -
消費者行動
2007年までに、人々は銀行取引、旅行の予約、ソーシャルメディアでの交流など、あらゆることをPCウェブ上で行うようになっていましたし、iPodなどのデジタルデバイスを持ち歩くことも当たり前になっていました。iTunesのようなアプリケーションは、すでにポータブルデバイス(iPod)でのデジタルコンテンツ購入を一般化していました。
この事例で伝えたいことは、過去の失敗に未来の成功要因が隠れており、全く同じアイデアでも、タイミング(外部環境)が違えば、結果も異なるという事です。
3)社会変容が成否を分けたネット食品宅配
次の事例は、1996年の創業したWebvanと2012年に創業したInstacartです。両社ともに同じ“オンライン食料品宅配”というビジネスですが、こちらも市場参入タイミングの違いによって成否を分けています。
1990年代~2000年初頭、ネット経由で食品を買うことはまだ珍しく、多くの顧客は「実物を見ずに生鮮品は…」と抵抗感が強かったはずです。そんな中でWebvanは「まだ始まっていない消費者行動」を引き起こそうと莫大な投資を行って失敗してしまいましたが、InstacartはAmazonなどの企業が作り上げた「オンラインショッピングの普及」と「ギグエコノミーの浸透」が重なった理想的なタイミングで参入しています。
Webvanの事例は、PMF前に急拡大して失敗した事例として語られていることが多いですが、ギグエコノミーが浸透する前の時代においては一定の初期費用は避けられなかったと思います。一方で、Instacartはマッチングプラットフォームとして、パートナー店舗を利用し、ドライバーをギグワーカーでまかなうことにより、初期投資を極小化しつつ爆発的な成長を遂げることができました。Webvanの経営陣も優秀だったと思いますが、ギグエコノミーを活用できる時代ではなかったことは大きな違いでした。また、消費者心理も大きく異なっていました。2010年代にはスマホ一つであらゆるモノを買う文化がすでに根付いており、コロナ過も大きな後押しになったと思います。
-
Webvan創業: 1996年
-
時代背景:
①オンラインショッピングはまだ黎明期で、クレジットカード情報をオンラインで入力することに抵抗を感じる人も多く、ましてや生鮮食品をネットで注文する習慣はなかった
②スマホは存在していない(当時は携帯電話といえばガラケー)
③ギグエコノミーや物流網の活用は出来ない
-
Instacart創業: 2012年
-
時代背景:
①消費者がネットで商品を注文することへの抵抗感が激減。Amazonの成功で宅配の利便性が広く認識されていた。
②スマホが完全に普及し、モバイルアプリが当たり前に
③「ギグエコノミー」の台頭により、UberやLyftなどの配車アプリが成功し、同様のモデルを他分野に適用するトレンド。

ここから学べることは、技術革新ももちろんそうですが、消費者行動の変化が事業を後押しする大きな波になり得るということであり、新しく流行し始めた他のサービスやプロダクトが消費者にどんな影響を与えているかを考えることも事業構想のヒントになるということです。
4)規制が流行を止めたオンライン音楽配信
1999年創業のNapsterはユーザー同士のPC間で直接ファイルを共有できる画期的な技術を用いていました。音楽ファイルを一度サーバーにアップロードする必要なく、各ユーザーのハードディスクから直接引っ張れる形です。
とはいえ、当時はブロードバンドがまだ普及し始めたばかりで、回線も不安定。MP3をダウンロードするのにも時間がかかる場合があり、ウイルス混入のリスクも大きかった。それでも「無料で好きな曲が手に入る」というインパクトが勝ち、多くのユーザーが利用していました。まさに波(市場)が存在していました。一方で、全く収益化は出来ていませんでした。
当然ながらレコード会社の著作権侵害を回避する仕組みもほぼ皆無だったため、当時の音楽ビジネスはCD販売が主な収益源の中でNapsterはそこに大打撃を与えたため、業界は“史上最大級の危機”として対抗しました。
結果的にRIAA(全米レコード協会)との訴訟に敗れ、わずか2年ほどでサービス終了に追い込まれました。
-
Napstar創業: 1999年
-
時代背景:
①まだ消費者にはストリーミングという概念が希薄で音楽は「CDを所有する」か「ファイルをダウンロードして所有する」かのどちらかで有料化・広告モデルへの転換ができなかった
②法整備もなく、音楽業界の強い反発があった
-
Spotify創業: 2008年
-
時代背景:
①NetflixやAmazon Primeなど、他のエンタメ分野でもサブスクリプションモデルが主流化。
②音楽も「定額で聞き放題」というモデルが受け入れられる土壌が形成著作権管理の法整備が進み、デジタル配信は防げない雰囲気
Spotifyは、2008年に創業し、この「音楽業界の反発と規制」という市場の波をせき止めている障壁を解消すべく、最初から音楽レーベルとの交渉を行い、合法的に楽曲を提供するビジネスモデルを構築しました。広告収入やプレミアムサブスクリプションの売上を権利元と分配する仕組みです。
Napster時代の“衝撃と混乱”をきっかけに、業界も「配信ビジネスを完全拒否するのは無理がある」と悟り、デジタル配信時代の著作権管理を整備しており、Spotify登場時にはすでに「ストリーミングは仕方ない、むしろチャンスとするしかないのかも」という雰囲気も生まれていました。
回線速度が格段に向上し、Spotifyはサーバーからユーザーへデータを送り続けるストリーミング方式を採用したことで、ファイルをダウンロードして所有する必要がなく、ネットが安定していれば常にリアルタイムで音楽が聴けるという技術的向上も後押しし、Napster時代のP2Pソフトは多少のPCリテラシーが必要でしたが、Spotifyは老若男女誰でも簡単に使える仕様になったことも大きく普及した要因でした。
これは、既に市場の波が到来しているものの、規制や技術的な障壁が波を遮断している、あるいは勢いを削いでいる事例です。
流行ったけど最終的に上手くいかなかったサービスの原因や規制が変化した領域を深ぼると実は大きなチャンスが眠っていることがあります。
3. 「外部環境変化」=タイミングを見極める
ここまで読んでいただいた方は、「優れた市場」かどうかは外部環境によって異なるため、市場参入の「タイミング」を見極める必要があり、外部環境(技術変化、消費者行動、規制動向など)の変化を掴むことの重要性を感じていただけたかと思います。
では、いざ「何をどう調べればいいのか?」まずは過去の失敗したビジネスを調べてみることをおすすめします。
過去の失敗原因は、未来の成功要因になり得ると考えています。過去に失敗したビジネスは表に出にくいので、探すのが難しいですが、現代はいくらでも知りようはあります。その事例をベースに、なぜ失敗したのかを分析し、その失敗要因を解消しうる外部環境の変化は起きているのか?今後起きるのか?といった観点で考えていくと、大きなヒントが隠れていると思います。
ここでは、いくつかの外部環境変化を観察する観点を整理してみます。
1)技術革新のスピードとコスト
-
コストカーブの転換点を捉える
通信インフラ、3Dプリンター、バッテリーなど、これらは年を追うごとに性能が上がり、製造コストが劇的に下がっていくことが多いです。これらは市場に芽が出始めた頃よりも、さらに早いタイミングで急速かつ一気に開花する可能性があります。過去の失敗事例の原因が、技術的要素にあるのであれば、それを解消しうる水準に到達するタイミングを測るのは、非常に良いと思います。 -
デバイスやサプライチェーンの新しいプラットフォーム
iPhoneやスマートグラスなどの革新的なハードウェアデバイス、あるいはAmazonやShopify、AIのAPIなど、既存のプレイヤーが整備しているプラットフォームやAPIをうまく活用できれば、小さなチームでも大きなインパクトを狙える可能性があります。新しく生まれたプラットフォームの与える影響を考察するという観点です。
例)YouTube誕生したのは2005年で、まだ4Gやスマートフォンは普及していませんでしたが、ブロードバンド接続が一般家庭にも行き渡り始め、動画がネット上でスムーズに見られるようになりつつありました。このタイミングで「誰でも無料で動画をアップロード・共有できる」仕組みが打ち出されたことで、YouTubeは爆発的に広がっていきます。もし2000年前後に同じサービスを出しても、回線速度や動画ファイルの容量的に成立しなかったでしょう。
2)消費者や顧客行動・心理の変化
-
他の成功サービスから波及する新しい習慣
UberやLyftと同様に、モバイルアプリとギグエコノミーの普及の組み合わせで市場が拡張された場合などから、すでに世の中に根づいた新しい習慣・心理を別の領域で横展開してみるという発想が有益な可能性があります。現在流行しているサービスや事業を観察し、それが本質的に捉えている消費者の行動が何かを考え、それが「実はこの領域でも転用できるかも?」と考えてみると、見えてくることがあります。たとえば、TSMCという時価総額63兆円、世界最大の半導体受託製造メーカーは、消費財領域で当たり前だったOEM製造という概念を半導体の領域に持ち込み大成功を収めました。
3)規制や法制度の変化
-
既存の障壁が下がる、消える瞬間を狙う(or 創る)
FinTechや防衛宇宙、医療・ヘルスケア領域などは、国や地域によって規制が緩和された途端に一気にスタートアップが参入し、花開くケースが多いです。自動運転やライドシェアなども、法改正次第で今までは実装不可能だったアイデアが実現可能になることがあります。先ほどのSpotifyの事例にもありましたが、規制の影響を受けやすい市場では、業界団体や当局、既存事業者などステークホルダーとの連携をあらかじめ計画し、「どう共存していくか」を最初から考えておくことも、重要となります。
4)マクロ経済・社会トレンド
-
人々が何に「不満」や「課題」を抱えているか
たとえば、急激に高齢化が進む社会では「介護」「在宅医療」「孤立防止」などが大きなテーマになる可能性が高いです。高齢者が増えると言っても、未婚率が上がっている現状を考えると「孤独な高齢者」が増えるわけで、それは従来の世の中と比べて大きな変化であり、将来的に大きな市場へ成長していく“必然”はないか?という視点をもってマクロトレンドを見ると、事業の種を探しやすくなると思います。 -
バブルや一時的トレンドではなく、構造変化か
長く事業を成長させていきたい場合、長期の観点は重要です。2~3年の流行で終わるものと、10年・20年で定着する社会変化かを考えることは重要です。「コロナ禍による巣ごもり特需は一時的なのか、恒常的にリモートワークが浸透するのか?」「ビットコインの値上がりは一時的かもしれないが、ビットコインがもたらす長期的かつ本質的な社会の実益は何か?」といった問いを立ててみると良いかもしれません。
例)AirbnbAirbnbがリリースされた2008年頃は、リーマンショック後の世界金融危機の真っただ中でした。人々は余計な出費を控えつつ、収入源を確保する手段を探しており、そこで「余っている部屋を貸し出すと収入になる」「ホテルより安い価格で旅行できる」という仕組みは大きな注目を集めたわけです。もし好景気のタイミングで同じ仕組みを出したとしても、「見知らぬ人を自宅に泊めるなんてリスクあるし、稼げるかどうかも疑問」という反応に留まっていたかもしれません。
5)複数の小波が重なる「波の合流点」
-
「技術×心理×規制」など複数要因が絡み合う領域
電気自動車(EV)は、バッテリー技術の進化、環境意識の高まり、政府の補助金政策など、複数の“波”が重なったことで一気に普及し始めました。イノベーションは“単独”で起こるわけではなく、複数の要素がタイミングよく組み合わさることで市場が急拡大することが多いです。過去の失敗事例も複数の失敗原因が存在します。それらすべてが解消しうるのか考えることが重要です。
まとめ)完璧に新しいアイデアは存在しない
「Everything is a remix」
クリエイティブの世界でよく聞かれるフレーズで「Everything is a remix」という言葉があります。つまり、どんな斬新なアイデアも、過去のアイデアを組み合わせたものに過ぎない、という考え方です。
iPhoneも前身のPDAであるNewton(Apple製) やPalm、さらにはGeneral Magicの技術・コンセプトがヒントになっていますし、SNSのFacebookも、先行のSNS(MySpaceやFriendsterなど)を参考に発展させた面があります。
過去の失敗に成功への答えが眠っている
完全に新しいアイデアのように見えても、何かしら類似する失敗例や事例が過去に存在することがほとんどです。あなたのアイデアが試されたかどうかは重要ではありません。
より重要な質問は、なぜ今がそのアイデアが機能する時なのか、何が変わったのか、何が過去とは異なるのかということです。過去の失敗理由を丹念に調べ、徹底分析することが非常に重要です。
同じアイデアでも、市場・技術・法規制のタイミングが整わないとうまくいきません。「あと5年待てばちょうど良かったのに…」 というのはよくある話です。過去の同種の失敗から「いつ何を待てば成功できるのか」を考察することは重要ですし、投資家が良く聞く「Why Now」という質問はまさにこれを聞いています。
いずれにしても「今は市場がない」と断言できる領域でも、タイミングやきっかけ次第で一気に拡大する可能性があります。大切なのは、自分たちが狙おうとしている市場が
-
本当に“まだない”のか(この先数年待っても成立しないか)
-
“これから作れる可能性がある”のか(待つことで成立するか、製品・サービス自体がボトルネックそのものを解消しうるか)
を見極め、必要に応じてピボットする柔軟性を持ち合わせることです。過去の失敗事例を単なる失敗と捉えるのではなく、将来の成功を暗示するヒントとして活かし、長期の未来の仮説を構築し、それに向けて短期ではピボットを繰り返していくことも想定しておくこと。
「プロダクト」そのものが最初から最高である必要はありません。改善していけばよいだけですし、でも市場を変えることは本当に大変ですし、これまで培った市場の知見もまた一からになってしまいます。
投資家やその事業に詳しい人から、「その事業アイデアは既に試されていて失敗しているから無理だ」なんて言われても、あきらめる必要はありません。あなたの事業アイデアが「今なら」成功する理由を、自分自身に問いかけてください。もし「なぜ今なのか」がはっきり説明できるのであれば、是非事業を立ち上げるべき時です。
新たな事業アイデアや起業構想を練りたい方、ぜひお気軽にご連絡ください
まだ曖昧なアイデアであっても、共に検証し、突破口を探っていくことに情熱を注いでいます。起業家の方や起業を検討中の方と共に、ビジネスの磨き込みから資金調達戦略まで幅広くサポートいたしますので、新しい挑戦に向けて、一緒に踏み出しましょう
詳しい活動は、以下のリンクからご覧いただけます:
あなたの「種火」を未来の「燈火」へ
すでに登録済みの方は こちら