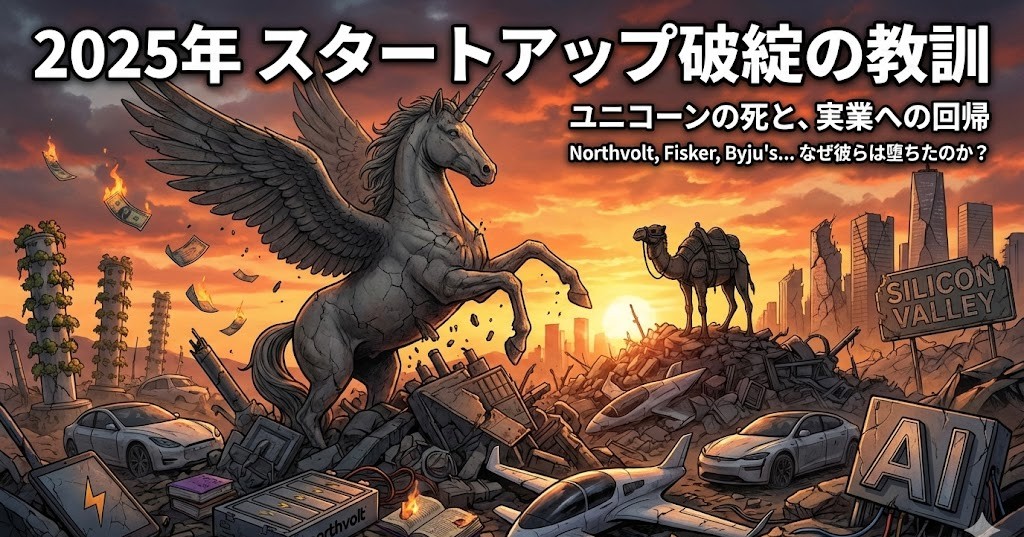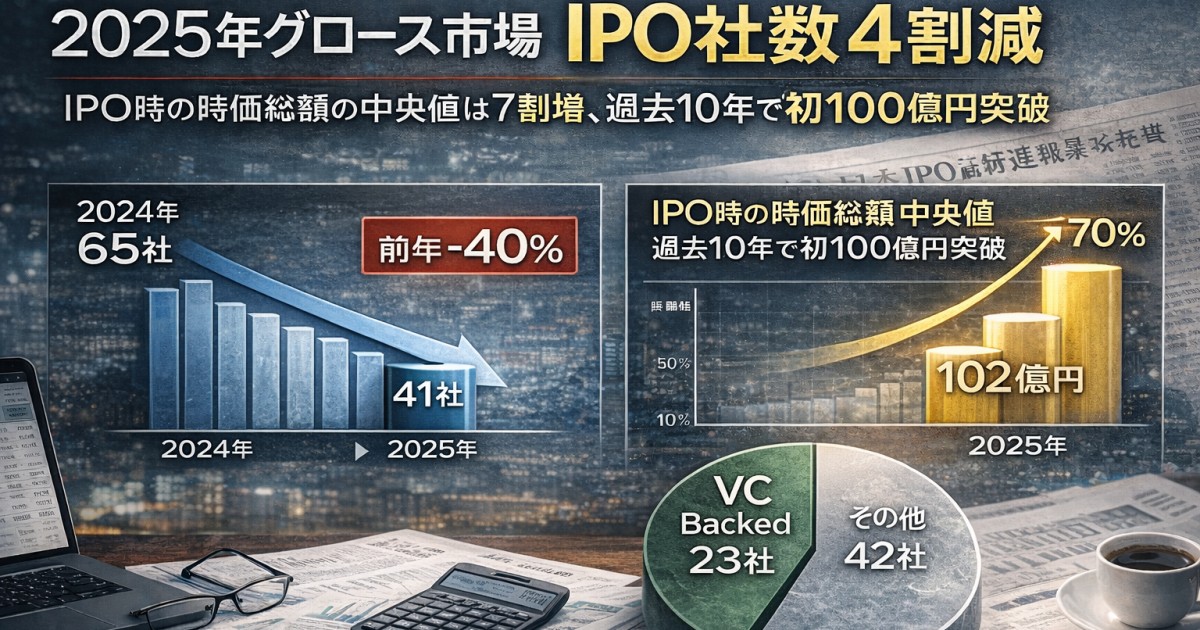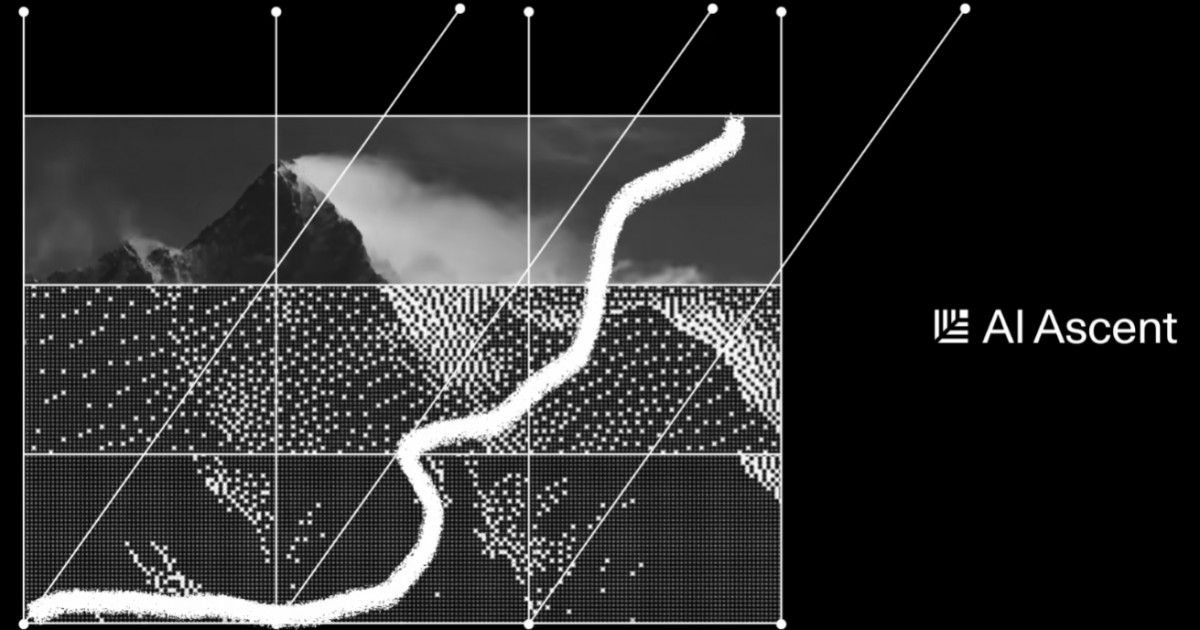“日本の常識”で、世界を熱狂させる起業家達
本記事では、Oishii FirmやAnyplaceなど、日本の常識を海外市場に持ち込んだ起業家たちの事例を掘り下げます。成功の背景にはどんな“違い”を見つけ、どうやって“価値”に変えたのか?を探ります。
グローバル市場を狙うスタートアップにとって、「文化・慣習・規制・生活様式」の差異は常にリスクとチャンスの両面をもたらします。とくに日米間では、多くの “当たり前”の違いがあります。
例えば、
味覚や食の嗜好・消費行動
-
米国では甘味・大容量・手軽さを好む傾向が強い
-
日本は季節感や見た目の繊細さ、限定品好きなどがある。
住環境やライフスタイル
-
米国の広い住宅での大量消費文化 VS 日本の狭小スペースを工夫して活用する文化
-
米国は家の中でも靴を履いたままだが、日本は必ず脱ぐ
通販・配送・コンビニ受取などの利便性
-
日本は当日・翌日配送などのクオリティが高く、コンビニインフラも整っている
-
米国は広大さゆえの配送難・保管サービスの需要の大きさが存在する
ブランドストーリーテリング
-
米国消費者は独自ストーリーを重視しつつも“効率”や”合理性”に強い価値を置く場合が多い
-
日本は“品質”や“繊細な顧客対応”への信頼を重視
「海外で受けるものが日本では鳴かず飛ばず」「日本で普通のものが海外で大躍進」などの現象が発生するのは、上記のような根本的な差異がたくさん存在するからです。
日本の当たり前を世界に昇華させた、起業家達の事例を深ぼっていきます。
2. Japan to Globalで成功した事例の分析
2-1. Oishii Farm:「日本の高級苺」で米国のイチゴ市場を席捲
Oishii Firmが米国に進出する以前、米国市場の一般的なイチゴは大きいが水っぽく、品種改良やブランド重視がそこまで進んでいない面がありました。
一方で、日本では「糖度が高く、見た目も綺麗な苺」が当たり前であり、とちおとめやあまおうなどの品種名で呼ぶのが一般的です。Oishii Firm創業者の古賀さんはアメリカに行った際に、アメリカのイチゴのまずさに驚愕したと語っています。
問題は、日本の素晴らしい苺が日本の独自の環境(ハチの自然受粉)でしか育たない事でした。
その問題を解決すべく、Oishii Firmは日本で蓄積されてきた施設園芸技術を米国の巨大市場に持ち込み、自社の植物工場でハチを使った自然受粉を再現するテクノロジーの開発に成功します。
その結果、“高付加価値の苺”を通年供給することが可能になりました。
彼らは、まずは富裕層や一流レストラン向けに50ドルもする超高級苺を売る戦略をとります。その結果、欧米では果物は「安価で大量消費」されるイメージが強いため、真逆の高級ブランド戦略で話題になりました。それが功を奏し、アメリカで日本の高級苺はヒットします。
日本人の「味へのこだわり」や職人文化、日本国内で培われた技術を武器にして、海外展開していった好例です。米国では“高品質な果物”自体が「非常識」ことがポイントになりました。
2-2. Ichigo:高品質で多様性のある「日本菓子」でグローバル進出
米国においては、間食文化が強く、基本的に各家庭で大量にスナック菓子をストックしています。その文化に最適化する形で、米国では大容量で単調な味の商品が多く、季節限定や多様なパッケージなどの文化が相対的に希薄でした。
一方で、日本のお菓子は「ローカル限定、季節限定、キャラクターコラボ」など圧倒的な多様性があり、小ロットで品質の高さ、美味しさも兼ね備えています。その結果、日本のお菓子は海外には稀有な魅力として映っていました。
ただし、海外の方々にとって、日本の新作菓子や地方和菓子はほとんど手に入りません。そこでICHIGOは、定期便のサブスクモデルで様々な日本のお菓子を小分けにして梱包し、海外向けに発送し始めました。
これが話題となり、SNSやYouTubeで世界中の“日本のお菓子ファン”に向けた口コミが急拡大していきます。徐々に日本の老舗メーカーとの信頼を構築し、自社倉庫・梱包まで内製化し、品質トラブルを最小化、飽きさせないために毎月異なるテーマ(地方特集や季節イベント)を打ち出し、海外顧客が継続購入しやすい仕組みを維持していきました。
海外から見た日本のお菓子は「多品種・こだわり・キャラクターコラボ」の魅力が巨大でしたが、手に入れにくいというボトルネックがありました。その障壁を取り払ったのがICHIGOでした。
2-3. KonMari:「片づけ」で心を整える日本式メソッドに世界が熱狂
米国は、日本よりも居住スペースが広いことが多いため、「モノが大量にあっても置ける」のが当たり前でした。とはいえ、それが故に大量消費・雑然とした収納に対して、疲れを感じる人も多く、“スッキリ暮らしたい”というニーズが増大していました。
近藤麻理恵(こんまりさん)が考案した「こんまりメソッド」は、喜びを感じるものを選ぶという変革的な基準を採用した、シンプルですが効果的な整理システムです。自分の内なる声に耳を傾け、「部屋にお辞儀する」など、日本的美意識と精神論を組み合わせた望む人生のためのスペースを作る独自メソッドとなります。Netflixを通じた全世界展開でエンタメ要素と片づけ術が融合し、日本発のユニークさが大きく話題になりました。
“単なる収納術”を超え、日常的行為(片づけ)を自己啓発レベルに格上げし、欧米でも受容されていきました。英語圏向けにビジュアルや用語を巧みに調整し、「日本式の物腰・精神性をあえて前面に出した」点が欧米人に強烈な印象を与えています。日本の「狭いから片づける」常識をそのまま輸出したわけではなく、海外の瞑想やメンタルヘルスの関心の高さを活かし、心の在り方や“捨てる技術”を“新感覚のメンタルメソッド”として翻訳したのが肝だったと思います。
2-4. ヨシダソース:甘辛しょうゆソースでアメリカンドリームを実現
アメリカではBBQ文化が浸透しており、バーベキューソースやトマトベースの調味料が大多数を占めていました。そんな中で、ヨシダソースは日系アメリカ人の吉田潤喜氏がアメリカ(オレゴン州)で1970年代後半に開発した独自の調理用ソースでした。
日本の醤油や砂糖、みりん、にんにくなどをベースにした、照り焼き風味の甘辛い調味料であり、アメリカにおいて「Teriyaki(テリヤキ)」というカテゴリーで人気を博しました。ヨシダソースは日本の伝統的な味付けをベースに、アメリカ向けにアレンジした「日系アメリカン料理」の一部に位置付けられます。
日本の“家庭の味”を焼き肉のタレとして使うだけではなく、バーベキューやステーキへの応用など使い道を広げ、アメリカの料理習慣に合わせて展開していきました。破産危機を何度も経験しつつも、周囲の協力で乗り越え、ジム・セネガル(コストコ創業者)との人脈や実演販売などを積極的に行い成功をおさめます。
日本的な“しょうゆベース”のソースは当時米国にないわけではなかったですが、広くは浸透していませんでした。このソースを「BBQ文化」に組み込むことで一気に普及させました。創業者の“キャラ立ち”も、単なる味の違い以上の価値を生み出しました。
2-5. Anyplace:日本の「ビジネスホテル」の感覚を米国で普及
米国では数週間~数カ月単位の出張短期滞在や“デジタルノマド”需要が急拡大しています。日本には安くて清潔なビジネスホテルが多数存在していますが、アメリカにはビジネスホテルというカテゴリーはあまり存在していませんでした。
Anyplaceは、高速Wi-Fi、デスク、モニターを完備し、ホテルや既存アパートメントにはない快適な仕事環境をあらかじめ整え、複数都市に同じクオリティの部屋を用意しています。ユーザーは都市を転々としてもAnyplaceで安心して仕事ができます。
出張やワーケーションでの物件探し(デポジットや電気・水道の契約など)を不要にし、既存の不動産サービスは追従が難しい設備やサービスで差別化し、日本のビジネスホテルの感覚をアメリカナイズして米国各地に展開していきました。
3. Global to Japanで苦戦した事例
海外発企業の日本撤退
Coupang
-
「ロケット配送」と呼ばれる超高速・無料配送、ネット通販での品揃えなどが支持され、韓国では時価総額数兆円規模に急成長。一方、日本への本格的参入は噂があったが、楽天・Amazon・ヨドバシなど既存プレイヤーとの競争や、地理的要因で宅配のアドバンテージを作りにくく、一部サービス展開にとどまり本格的には根付かなかった。
-
日本は既に“翌日配達”が標準化されている上、コンビニ受取や地域物流網が整備されていて、韓国的なスピード配送があまり目新しくなかった。
Noom
-
Noomは、行動心理学に基づいた専属コーチの指導でダイエット成功まで伴走してくれるアプリで、過度な制限なく減量や生活習慣の改善を図るもの。アメリカ発のサービスで、短期的なダイエットではなくカロリーや食事のコントロール方法といった知識の習得を促すことで、短期的な減量ではなく、生涯を通じた行動変容を目指している。有料版は月額月額5千円程度。
-
Noomは米国では2021年6月に約590億円の資金調達を行い、成長を続けているが、2021年7月16日に日本市場からは撤退。撤退の具体的な理由について公式な発表はないが、米国と異なり日本は救急車が無料で、国民皆保険制度が故に病気になっても安く済むため、予防の意識が低く、肥満率も米国より低いことが顧客の月額5千円の課金を渋らせたと予想される。
自国以外の市場に参入する際は、「その国固有の流通・決済・消費文化にどれだけ合わせられるか」が成否を分けると言えます。韓国や米国で成功したスキームが、そのまま日本人にとっても魅力かどうかは別問題ですし、逆に言えば、日本人にとっては普通でも海外の方にとっては魅力的にうつる面も多数存在すると言えます。
総括:違いを恐れず“新しい当たり前”を創る
日本人起業家が海外で成功を目指す場合も、逆に海外企業が日本展開を目指す場合も、「文化的・制度的ギャップ」の中に重要なヒントが隠れていると感じます。
大手プレイヤーであろうとローカル特有のニーズを見誤れば撤退を余儀なくされる一方、スタートアップであっても、その差異を的確に捉えれば大きく飛躍できるチャンスとなります。
「当たり前の違い」を“ただの壁”ではなく“機会そのもの”と見ること。
成功事例(Oishii Farmなど)も苦戦例(Coupangなど)も、いずれも“違い”が軸になっていることに変わりはありません。起業家は、その違いをどう味方につけるか?
そこにこそ、競合に先駆けて新しい価値を作る鍵があると感じます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
新たな事業アイデアや起業構想を練りたい方、ぜひお気軽にご連絡ください
まだ曖昧なアイデアであっても、共に検証し、突破口を探っていくことに情熱を注いでいます。起業家の方や起業を検討中の方と共に、ビジネスの磨き込みから資金調達戦略まで幅広くサポートいたしますので、新しい挑戦に向けて、一緒に踏み出しましょう
詳しい活動は、以下のリンクからご覧いただけます:
私(田中 洸輝)について
・立教大学観光学部卒、体育会アメフト部第82代主将を務める
・2018年に東京海上日動火災保険株式会社入社。中堅企業の経営支援業務に従事。
・2020年にAccenture株式会社入社。経営戦略立案、DX、PMOに従事。
Accenture Ventures にてアクセラプログラムの運営、スタートアップと協業検討等に従事。
・副業的にSolo起業し、初年度で1.2億円収益あげるもスタートアップ的な起業を志向し、会社休眠を決断。VC主催の起業家イベントに参画する経験を経て、将来VCを設立/&起業することを決意。
・2022年に大手独立系シードVCのインキュベイトファンドへ参画。アソシエイトとして新規投資先の発掘、投資先企業のバリューアップ業務、LP Relation等のファンド業務全般を担当。
失われた30年 ~30歳のVCが目指す「日本を、世界の主役に」~
1994年生まれの私は、2025年現在30歳となり、ずっと失われた●●年と言われ続けてきた世代です。自分の子供や孫世代はそう言われない、素晴らしい時代に生まれたと感じて欲しい、そんな思いで日本の経済全体にポジティブなインパクトを与えること目指して、VCをしています。
(同い年のメジャーリーガー大谷翔平さんが、あれだけ凄いインパクトを日本に与えてくれていることは尊敬してやまないですし、同じ年に生まれただけで嬉しいですが、憧れすぎずに、少しでも追いつけるよう必死に頑張っていきたいです。)
父も母も起業家という家庭で育った私は、バブル崩壊の余波を食らって苦しんだ時期と裕福な時期を両方経験し、その中で起業家として最盛期に近づく様々な人々と起業家として苦境の時期に離れていく人々をたくさん見てきました。いい時も悪い時も、父も母も常に孤独に見えました。それは
真に心を許して、高いレベルで真剣に事業の相談が出来る相手が誰もいないように見えたからです。
そんな思いを持っていた中で、「1兆ドルコーチ」という1冊の本に出合います。 アメフトのコーチ出身でありながら、40代でビジネスの世界に入り、Apple創業者のスティーブジョブズの師(葬式でのスピーチが有名)であると同時に、グーグル創業者たちを育て上げ、アマゾンのベゾスを苦境から救ったという逸話で有名な方であり、彼が支えた起業家たちの時価総額を合算すると1兆ドル=約150兆円を超えると言われた伝説の人です。いずれ彼のようになると強く、決意しました。
また、私は「財を遺すは下,仕事を遺すは中,人を遺すを上とする」という言葉を大事にしています。では、どんな”人”が遺せたらいいのか?自分はどんな人達なら死ぬ気で支えたいと思えるのか?自問自答した結果、社会を良くするために革新しようとする大きな志を持った挑戦者や革命家=現代の起業家であるという答えに達しました。私はそんな人々が増えれば増えるほど、世界はもっともっと良くなると心から信じていますし、そんな素晴らしい起業家たちの背中を支え、父や母のように孤独に見えない、孤独にさせないようにしていきたいと考えています。
私のブログ等がきっかけで、起業するあるいはスタートアップに参画する選択肢を選ぶ人が1人でも増えるなら本望ですし、挑戦するきっかけとなる最後の一押し、諦めたくないけど心が折れそうになっている最後の支えであり続けるという覚悟を持って、日々VC業に取り組んでいます。
スタートアップや新規事業に関するご質問やご相談があれば、いつでもお気軽にお声がけください。未来を切り拓く挑戦を、共に進めていきましょう!
あなたの「種火」を未来の「燈火」へ
すでに登録済みの方は こちら