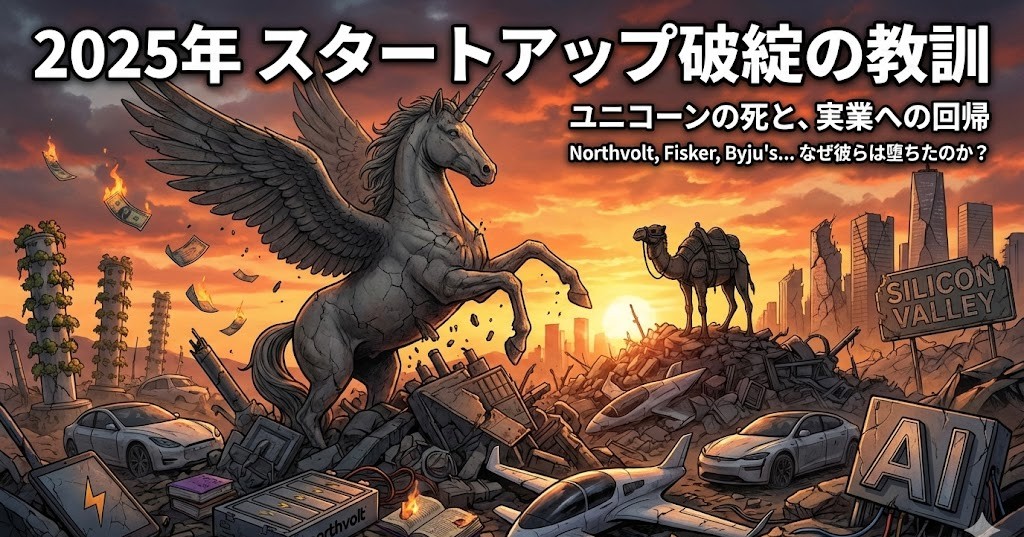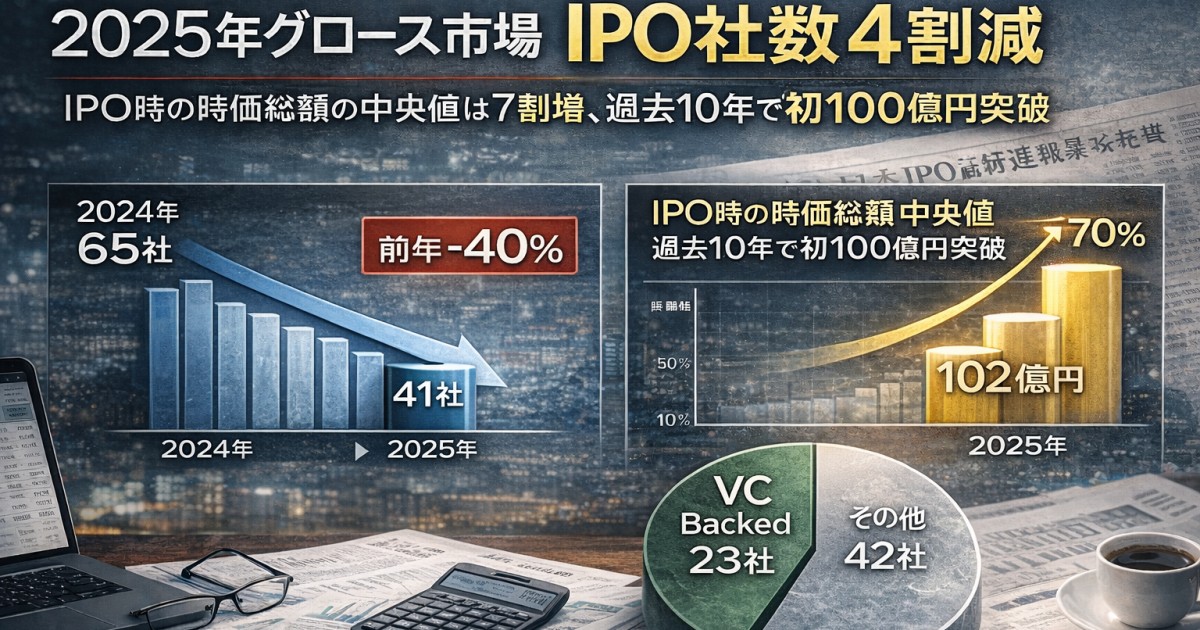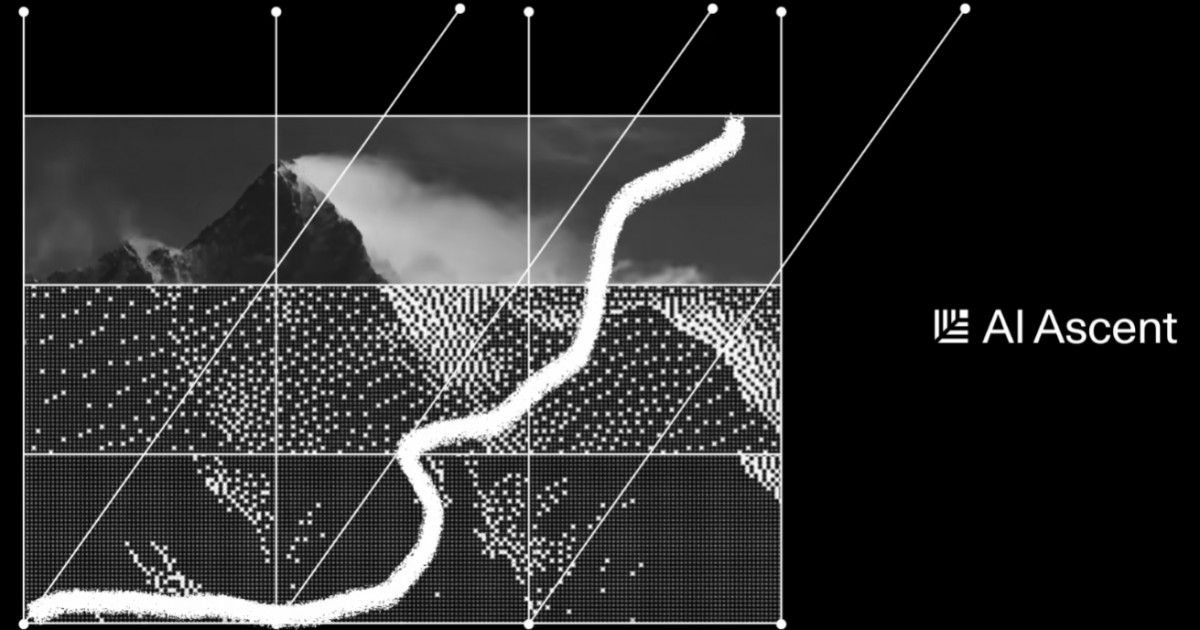逆境からの再出発:京都発 ”Notionの創業物語”
今や世界中で使われるNotionは、実は一度倒産寸前となり、京都で奇跡の復活を遂げたスタートアップです。なぜシリコンバレーを離れ京都へ移住したのか?知られざるNotion再建ストーリーに迫る。
田中 洸輝 (IncubateFund VC)
2025.03.20
読者限定

はじめに 〜京都発のグローバル企業Notionに迫る〜
今やほぼ知らない人がいない生産性向上ツール「Notion」
この記事は無料で続きを読めます
続きは、5306文字あります。
- 第1章:シリコンバレーでの挫折 〜“成功しそうでしない”プロダクトの苦悩〜
- 第2章:京都への移住 〜SFから離れて生まれ変わったプロダクト〜
- 第3章:世界へ羽ばたく 〜再建からユーザー激増への転換点〜
- まとめ
すでに登録された方はこちら