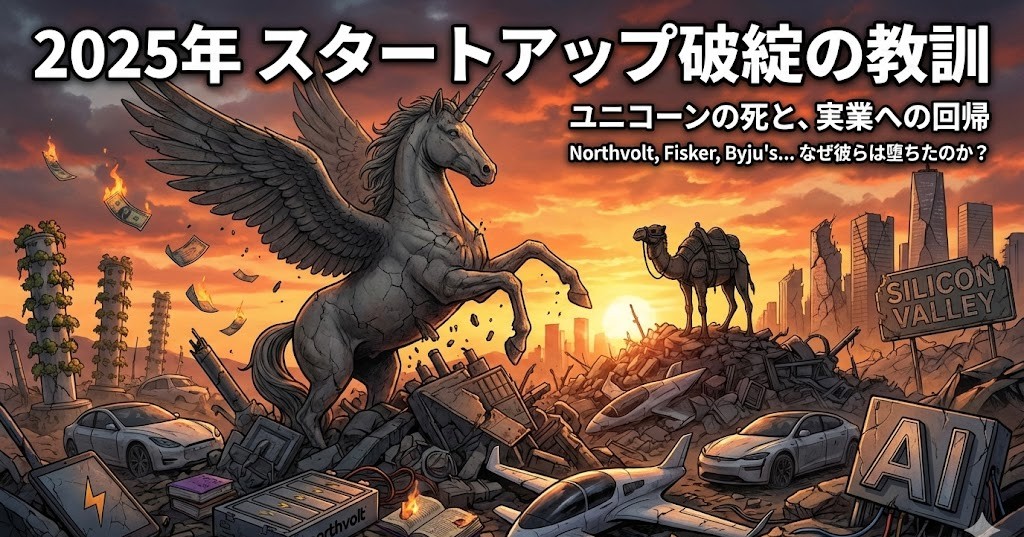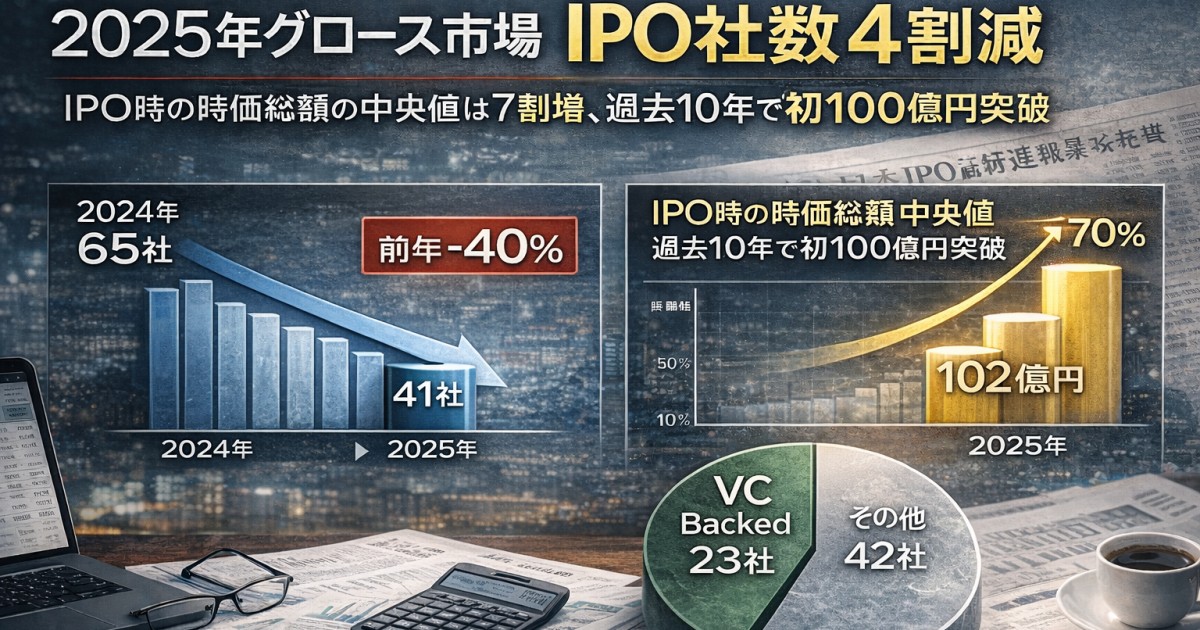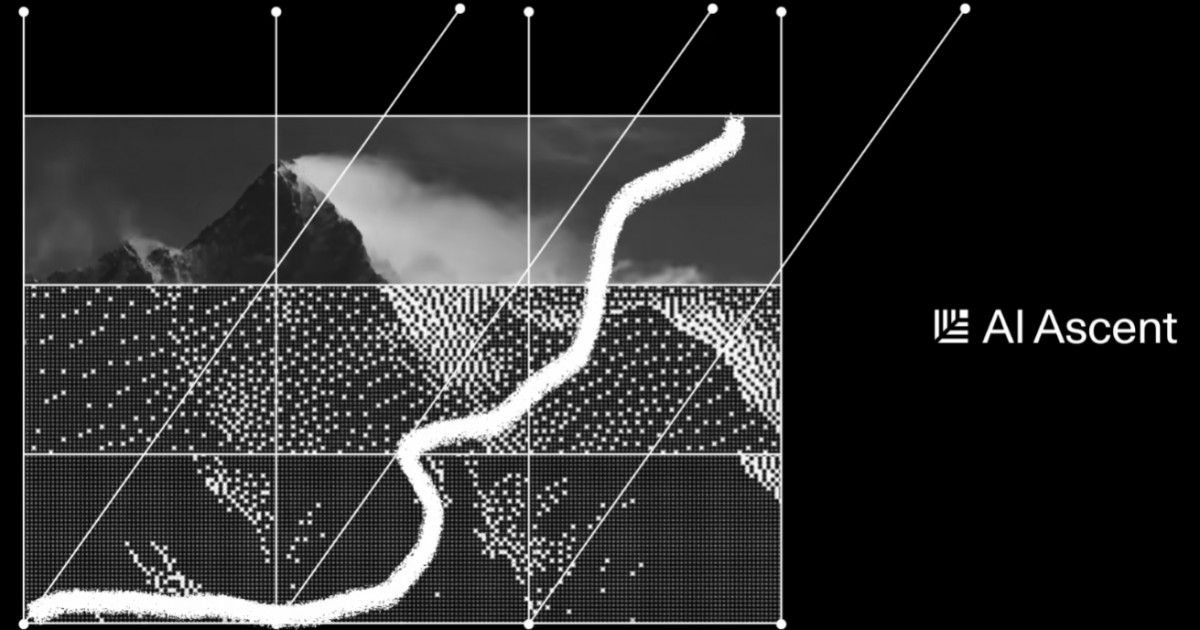2025年 注目の起業テーマ
~社会/規制/技術の変曲点から生まれる新機会~
この記事では海外事例や具体的アイデアを交えて、注目テーマを深掘りしています。

※後述する起業テーマは私のごく限られた前提知識や経験に基づいているものですので、様々なアドバイスやご意見、熟読する価値のあるブログや記事などの情報をどしどし頂戴できますと幸いです。
Future of Work
1.Physical AI (ロボティクス)
2.Vertical Compound AI
Japan Dynamism
1.Defense Automation
2.Specialized Risk Solution
(Other)
・AI Personal Worker
・Luxury Entertainment
Future of Work
1.Physical AI (ロボティクス)
【今、起業すべき理由】
・熟練労働者の大量引退による自動化や省人化ニーズの急拡大
・OSSや技術革新に伴うロボット開発や生産コストの低減
・地政学リスクによる製造業生産拠点の国内回帰のトレンド
・政府や大企業のロボティクス領域への支援拡大
・生成AIの進化×ロボティクス(日本の強み)領域
2025年は団塊の世代が75歳以上となり、労働力不足と急速な少子高齢化が進む中で、多岐にわたる分野で自動化や省人化ソリューションがより求められてくるはずです。
特に、60歳以上のベテラン技術者が急速に退職期を迎えており、製造業や建設、インフラメンテナンスなどで技術継承問題が喫緊の課題となりつつあります。
そんな中で、生成AIやセンサー技術の進歩、ロボット用開発プラットフォームの勃興等により、ロボットの開発コストが低下し、学習速度も上昇したことで、従来のロボットの限界を超えて顧客に価値提供できるロボットを開発できる可能性が高まっています。世界各国で人件費が増加傾向であり、人より安い労働力として、ロボットの選択肢が増えていく可能性が高いです。事実として、国際ロボット連盟(IFR)の報告によれば、産業用ロボットの導入台数やロボット密度は急上昇し、プロフェッショナルサービスロボットの需要も拡大しています。
国内生産回帰や地政学リスクへの備えとして、日本国内での生産や在庫配置が見直され、製造拠点を国内に戻す/新設する動きもあり、もともと製造業が多く中国に次ぐ世界第2位のロボット稼働大国である日本は実証検証の場が得やすいという優位性もあります。
経産省やNEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)なども、ロボットや自律制御技術、AI技術の研究・事業化をサポートする支援策を強化しており、さらに、安全基準や品質へのこだわりが高い国内企業の要求に応えられる技術やサービスは海外展開の可能性も広がるため、長期的な市場成長を狙う起業家の方にとっては魅力的な挑戦分野だと思います。
今後はロボット開発向けのソフトウェアプラットフォームや他社製ロボットを活用した総合自動化コンサルティング、高度な技能を持つロボット遠隔操作技師といった仕事の需要も加速すると考えています。Physical AIは、長期投資・R&Dリスクを要するかつ、Go to Marketの難易度も高い領域ではありますが、日本の強みである製造業や観光・外食・小売産業などに革新をもたらす非常にポテンシャルの大きい起業テーマとして大いに注目しています。
【海外スタートアップ事例】
・10Beauty
“Intelligent Beauty”プラットフォーム「古いネイルの除去→爪のファイリング→甘皮処理→新しいポリッシュ塗布→乾燥」まで行う世界初の自動マニキュアマシン「The 10」を開発・販売。約70億円を調達。百貨店や大手コスメチェーン、高級サロンなどに「The 10」を設置し、すでに1,000台分の「プレ・オーダー」が完了している、かつ年額$13Mのポッドサブスク収益が見込める。
・RIPCORD
Intelligent Document Processing (IDP) 。大量の紙書類を持つ企業や官公庁向けに「ホチキスの除去」や書類の丁合、スキャン等の工程を自動化するロボティクスハードウェアと、データ抽出・分類を行う独自のAI/ソフトウェアを組み合わせた紙書類の自動デジタル化サービス。Kleiner Perkins、Google、Luxから約50億円を調達。Appleの共同創業者Steve Wozniakも出資。
・Flock Safety
監視カメラのハードウェアとAIを活用した自動車ナンバープレート認識(ALPR)技術を開発・提供。RaaSモデルで提供することで主要な競合他社と比較すると、同じコストで20倍以上のALPRデバイスを設置可能。2万5千施設に導入済みで100億円のARR。全米で報告された犯罪の5%の解決に貢献している。
・Physical Intelligence
ロボットの特定タスクごとにソフトウェアを開発する必要性をなくし、あらゆるロボットで動作するソフトウェアの「π0(パイゼロ)」を開発。2024年にAmazonのジェフ・ベゾス、Open AI、VCのThrive CapitalとLux Capitalから約3,000億円の評価額で約600億円を調達した。
・Viam
元MongoDB共同創業者兼CTOが2020年に設立したハードウェアの構築、監視、データ管理を簡素化する包括的なオープンソースプラットフォームを提供する。2024年にUnion Square Ventures、Battery Venturesが主導したSeries Bで約60億円を調達し、資金調達総額は約135億円に。
・Figure
AI制御や自律学習技術を導入した倉庫・物流・製造現場などで作業可能な「汎用ヒト型ロボット」開発。2023年に約100億円前後を調達。TeslaやApple出身のロボティクス/EVエンジニアが創業。
【起業アイデア例】
・危険/僻地環境向けのAI遠隔操作+自立モード切替式の産業用ロボット
・中小製造業や官公庁向け「超低コスト」ハードウェア&AIのRaaSプラットフォーム
・ロボット導入シミュレーションソフト等を活用した自動化/無人化特化コンサルティングファーム
・複数用途対応可能なモジュール型小型ロボットアーム+AI制御プラットフォーム
2.Vertical Compound AI (+M&Aロールアップ)
【今、起業すべき理由】
・汎用AIモデルの急速な技術革新(高度化・実用化)が進行
・深刻な労働力不足とAIビジネスモデルの進化「Seling Work」
・単独機能に特化した「ポイントソリューション」の増加
・「2025年の壁」老朽化するレガシーシステムの急増&DXトレンド
・後継者不足による地方中小企業の事業承継ニーズ
大規模言語モデル(LLM)が急速に進化し、より専門性の高い用途で利用されるニーズが高まっています。医療、金融、法務など特定業界の実務レベルでの活用可能性が拡大しており、特に音声やメール、チャットなどのコミュニケーション領域は本格的な実用段階に入り始めたと感じています。
海外では「伝統的で地道な作業を伴う仕事」(経理、カスタマーサービス、不動産管理など)への投資が活発化しており、これらのサービスビジネスは、その多くが最終的に全国展開することでかろうじて利益を創出しているため、VC投資家からあまり注目されていませんでしたが、AIの進化で1,000人が必要だった仕事が、100人、10人で可能になるとすれば重要なビジネス機会だと思われます。日本の強みである、ゲームや漫画などのエンタメ/IP領域におけるAIの活用も大注目しています。
医療・介護・物流・建設などの労働集約的なサービス産業では特に人材不足が深刻化しています。
「今後 5~10 年で数十万人単位のスタッフ不足が生じる」と推計されており、AI導入のインセンティブが高まっています。AIは業界特化することが差別化の究極の原動力となり、
ソフトウェアを新たな労働力に変えていくでしょう。
また、海外のAIスタートアップでは「IT 予算」ではなく「人件費予算」を取りに行く新たなビジネスモデル(作業や仕事の成果に連動した新しい料金体系)「Seling Work」が主流になってきており、これらが日本でも主流になれば、IT 部門の予算は限られる一方で人件費が一定発生する労働時間が長い業界に導入されやすいのではないかと考えています。
医療(診療報酬請求、電子カルテ、看護師シフト管理)、保険(査定・審査、顧客説明)、介護(ケアプラン作成、請求事務)など、業界固有の業務フローと規制要件が多く、大量の事務作業と規制対応が存在する業界においては単一機能だけでは根本的な課題解決が困難です。日本独自の業務フローも多々存在し、海外の製品に対しても参入障壁があります。
各業界ごとの規制・専門知識にフィットする形で深くカスタマイズされたAIソリューションを提供できれば、汎用型AIでは対応しづらい領域を掘り起こせますし、データ資産の囲い込み(業界特化の機密情報等)ができ、一度導入されると切り替えコストが高く競合優位を築きやすいと考えます。
昔のレポートではありますが、経産省のDXレポートでは2025年に21年以上稼働しているレガシーシステムがシステム全体の6割を占めるとのことで、老朽化や複雑化、ブラックボックス化している既存の基幹システムやSalesforce、Workday等を押しのける統合型ソリューションを提供できうる一隅の機会が訪れているかもしれません。
周知の事実ですが、急速な少子高齢化による後継者不足の問題もあります。経済産業省のデータでは、年間数万社単位で事業承継に課題を抱える企業が生じているとの推測もあり、M&Aプラットフォームを介した買収・統合が増加傾向です。PEファンドなどが地方の中堅企業や上場企業の買収を積極化していますが、日本の企業の99%を占める中小企業はまだまだ対象になっていません。
黒字でニッチな強みを持つ優良企業は多く存在しているため、AI等を活用した業界特化のPMI戦略を構築できれば、買収後の収益性やスケールを飛躍的に高められる可能性が高いと考えています。
汎用モデルの進化は著しいですが、求められる機能の80%はカバーできても、残り20%の領域特有要件が導入・運用を妨げる決定打になるケースがありますし、最終的にユーザーに選ばれ長期利用されるのは、業界を深く理解して真の問題解決ができるプレイヤーとなる可能性が高いと私は考えています。単なるAIによる技術差別化ではなく、業界独自の規制やオペレーション全体を深く理解し、複数機能を横断的に提供してデータを包括的に取得・活用することが重要ではないかと考えています。そのため、AIの知見と特定業界の知見の双方を兼ね備えた組織構築が必要となるでしょう。
また、ロールアップについては、M&Aや業界固有の専門知識を持つ人材の確保、M&A仲介/業界団体との連携、シナジーを確実に創出する実務力など、高い実行能力が必要とされるためこちらも難易度は高いですが、今後も少子高齢化と労働力不足は不可逆的に進むと予想されるため、超高齢化先進国日本で必要とされているテーマとして注目しています。
【海外スタートアップ事例】
・Crete Professional Alliance
監査法人や税理士法人などをロールアップ(買収)し、バックオフィスや顧客管理、コンプライアンス対応を標準化・AI自動化して収益性を高める戦略。各事務所が持つ顧客資産や地域ネットワークを統合し、相互紹介・クロスセルを実施。累計投資額は約500億円超と推定。
・Harvey
法律業務に特化したVertical LLM(Legal AI Agent)を開発。膨大な法令・判例データベースと連携し、弁護士の文書作成やリサーチをサポート/自動化するSaaSを提供。将来的にはデューデリジェンスやM&A契約支援などへの展開も示唆。SequoiaやOpen AIから約30億円ほど調達。
・anima
病院や自治体など複数の関係者を巻き込んだAIヘルスケアプラットフォーム。医療相談、臨床ノートの自動生成まであらゆるものを自動化し、患者からの問い合わせの85%を1日以内に迅速に解決。一般的な11~14日という期間を大幅に改善。約20億円を調達。YCombinatorも資本参加。
・Air.ai
「AIコールセンター」音声通話の対話をほぼリアルタイムで行う音声合成・音声認識技術を自社開発。小売店舗や飲食店、サービス業向けに“電話応対の自動化”を提供。既存の電話回線やクラウドPBXと連携し、顧客からの予約受付や質問対応をAIが音声で行う実証を開始。約15億円調達。
・ServiceTitan
北米を中心に電気工事・水道修理などの“ホームサービス事業者向け”に特化した統合ソリューション。スケジューリング、スタッフ配置、在庫管理、顧客管理、決済などを包括的に提供。最近はAIによるコールセンター対応支援や、予防保守提案の自動化などに注力。時価総額数千億円と推定。
【起業アイデア例】
・伝統的サービス産業(介護/医療/観光など)の領域特化「Staffing & Operations AI」
・サービス産業向けの自動応答から在庫管理まで一括管理するAI Worker
・規制や照会応答業務が多い産業(金融/保険/建設など)向けLLM+音声AI
・特定伝統産業(士業/保険/金融/不動産/農業/観光など)のロールアップ×AI
・AIを活用したワークフロー自動化コンサルティングファーム
Japan Dynamism
1.Defense Automation
【今、起業すべき理由】
・政府国防予算の急激な増加と政策支援拡充
・地政学リスクの増大とトランプ政権
・技術的転換点(AI、センサー、Edgeコンピューティング等)の到来
日本政府は、防衛力整備計画期間(2023~2027年)の間に総額43兆円程度を計上し、うち2025年度は最大規模となる8.7兆円の当初予算案を閣議決定し、過去最高額を連続更新中です。防衛装備庁も「無人アセット防衛能力」「指揮統制・情報機能の強化」「宇宙・サイバー・電磁波領域」など、無人化システムやAI活用を含む領域での投資に注力する旨を公表していますし、政府全体としても「DARPA的組織の創設」や「スタートアップとの協業フレーム構築」を打ち出しつつあり、かつてのような「大手防衛企業しか参入しづらい」構造を改変する動きが出てきているため、アーリーステージのスタートアップとも連携できる土台が少しずつ整備されてきていると感じています。
その背景には、北朝鮮の核・ミサイル開発、中国の海洋進出、ロシアとの北方領土、AIによるサイバー攻撃側の進化等により、従来より日本の防衛課題が顕在化している上に、ウクライナ危機に端を発した欧州の軍拡やNATO圏の調達拡大がアジア・日本にも影響を及ぼしていると考えられます。
第一回トランプ政権の「防衛費増額要求」なども踏まえると、同盟自体はあるものの、防衛費増額要求を含む駐留経費、貿易負担などトランプ氏特有の「同盟国にもコスト負担を求めるアプローチ」が繰り返されることが予想され、自律的な防衛力強化を急ぐ動機になっています。
技術的な観点から言えば、ドローンや無人機が従来の単なる遠隔操作レベルから「自律型AI制御」(スウォーム飛行等)に進化してきていますし、衛星コンステレーション(複数小型衛星)による低コスト・高頻度観測やローカル演算が進み、情報のリアルタイム取得・即応性が飛躍的に高まってきています。つまり、「有人拠点の存在しない遠隔地でも通信が確保される状況」が整いつつあり、これは無人化の加速要因となり得ると考えています。
海外を見ると、わずか数年で数十億〜百億ドル規模の評価額に成長するDefense Techスタートアップが多数出てきており、「Defense Tech」という言葉が市民権を得てきているように感じます。
一方で、アメリカの国防総省やCIA系ファンドのIn-Q-Tel等から初期資金や契約を得ていた事例も多く、日本においては官需と民需(災害対策、警備、インフラ管理等)を両睨みした立ち上げが必要となる可能性が高いです。日本国内世論は、防衛産業そのものへの反発も依然根強いことも懸念材料です。技術・社会環境の転換点が来ており、大手防衛企業や従来の重工系でカバーできないソフトウェア/AI領域でスタートアップの役割が大きいと考えています。
日本社会にとって非常に重要な領域であることは間違いありません。
【海外スタートアップ事例】
・ARMADA
戦地などでも活用可能な堅牢で可搬型のデータセンターやオンプレやクラウド、遠隔地でリアルタイムAI解析が可能なエッジコンピューティングソリューションを提供。衛星通信(Starlink)との組み合わせで携帯回線が届かない場所でもインターネット接続し、大量データを必要に応じてクラウドへ送るハイブリッドモデルが可能に。Microsoft等から総額150億円を調達。
・Saronic
自律移動型船舶を開発。元ネイビーシールズのCEO。8VC, a16z, LightspeedなどからシリーズAで約80億円を調達。海軍と2つの研究開発契約を結んでいる。伝統的に大型艦艇の製造に重点を置いてきた造船会社が自律型の設計能力と専門知識を欠いているところに勝機を見出したとのこと。
・Vannevar Labs
電波音声や無線・通信傍受などリアルタイムで外国語翻訳/テキスト解析するAIプラットフォームを政府・軍・情報機関に提供。創業チームに元政府・軍事関連及びAI人材が多い。総額で約140億円を調達。15以上の政府機関の軍事基地で戦場情報の処理や敵対者への対処などに利用。年間$25M以上の収益を上げており、5年足らずで黒字化した。
・Anduril
AI・自律システム・センサー技術を組み合わせ、国境警備や無人監視プラットフォーム等を提供。海中ドローン、無人機、監視システムなど多角的に開発。元Facebook製品開発責任者・Oculus創業者らが設立し、ソフトウェア主導で急成長。国防総省や国土安全保障省など、米政府機関との複数大型契約を獲得。昨年2024年に約2,200億円を調達しており、時価総額は1兆円を超えると推定。
・Shield AI
AIパイロットと呼ばれる自律飛行ドローン技術を開発。GPSが使えない閉鎖空間でも飛行し、偵察や監視ミッションを自動化。特殊部隊向けの屋内/市街地用無人機(Novaシリーズ)を展開し、狭所や視界不良環境でもAI搭載ドローンが自律飛行できる。時価総額は約4,000億円と推定。
【起業アイデア例】
・GPS不安定環境下での自律飛行/走行/航行ソフトウェア+ドローンの複数機同時制御AI
・衛星/レーダー/音響/赤外線といった複数センサーを融合した即時の脅威検出・追跡AI
・無人ロボット等の長時間運用を可能にする省電力技術や次世代電源、量子暗号通信などインフラ
・エッジAI+衛星データを活用したソリューション(部隊配備や補給を最適化など)
・運搬が容易で過酷な環境下でも即時接種できる高い栄養価と味が担保された食事
2.Specialized Risk Solution
【今、起業すべき理由】
・損害保険業界の不祥事に対する規制強化
・損保大手4社の寡占状態を打破する競争促進政策
・コロナ過とDXトレンド
・リスク対策の多様化/複雑化/高度化
アメリカも日本もInsurTechブームが一巡していますが、私は2025年から特に損害保険業界において、大きなチャンスがあるのではないかと考えています。損保業界は「大手4社で保険料収入の9割を握る」とされ、事実上寡占状態でした。保険料率算出機構は自動車等の主要な保険料率しか公開しておらず、主要な損保領域でのスタートアップ参入は事実上不可能でした。
しかし、大手4社による事実上の寡占と度重なる不祥事を受け、2024年12月に金融庁が示した報告書案にて、「損保への新規参入を促す」「ブローカーを増やす」「保険代理店規制を強化する」といった複数の改革案が並行して検討されており、企業向け損害保険を中心に、保険会社側の競争力を削ぐというよりは保険業界に「新規参入しやすい構造をつくる」方向性で規制が変わる千載一遇のタイミングが到来しており、スタートアップとしてはこれをチャンスと捉えられます。
具体的には、金融庁は不祥事防止と健全な競争促進のために、損害保険料率算出機構の役割をサイバー保険など新種保険へ対象を拡大する、ブローカーと代理店の協業解禁などを検討しており、これはサイバー保険や運送(物流)保険、経営者賠償責任保険など、新種保険へ新規参入する企業にとって、リスク評価や料率設定のリソースを削減できるメリットがあります。とりわけ、スタートアップがいきなりアクチュアリーや大量の保険統計データを持つのは困難ですが、公的に算出された料率の参照やテンプレート活用が可能になれば、事業立ち上げのハードルは大きく下がります。
また、
日本の保険業界では保険代理店経由が約9割を占め、ブローカーのシェアは1%未満にとどまります。ブローカーの参入障壁が高いことや、規制上、代理店とブローカーの協業が認められていなかったことが一因とされます。ところが、金融庁はこの規制を緩和する意向を示しており、それによりブローカーが代理店と連携して多様な保険商品を企業・個人に提案しやすくなります。「中立的な立場でリスク評価を行う存在」が増えることは、保険会社のサービスや価格設定の透明性を高め、かつ新規参入企業にとっても契約獲得機会が拡大する可能性を意味します。
伝統的な火災・自動車・傷害保険は市場が飽和状態に近い一方、サイバーリスクや自然災害リスク、運送リスクなどはデータの蓄積が比較的少なく、「今からでも新規参入で大手と勝負できる可能性がある」分野といえます。
当然ですが、日本国内でもスマホやオンライン完結の保険商品への需要は徐々に高まっています。特にコロナ禍を経て様々な業界でオンラインでの契約やリモート・非対面での手続きが定着し、UI/UXの重要性が増しました。保険業界は非常にアナログな業界のため、UI/UXに注力することで既存大手ではなく新規参入保険会社のサービスも選ばれやすい地合いが整いつつあります。
今日の保険市場においては、単純に「事故や損害が発生した際に保険金を支払う」だけでは、もはや十分な付加価値を提供できない時代になりつつあります。これは、企業や個人が直面するリスクが以前にも増して多様化・高度化しているからにほかなりません。たとえば、自然災害の激甚化やサイバー攻撃の巧妙化、あるいは個々人の働き方やライフスタイルの変化に伴い、従来の画一的な保険商品では補いきれない領域が顕在化しています。その結果、単なる「保険金の支払い」だけではなく、「リスクそのものをどう軽減し、発生した際にはどう迅速に対処するか」を包括的に支援するソリューションの需要が高まっていると考えます。特定のリスク領域に深く精通し、「事前の予防サービス」「パーソナライズされた保険提供」「事後対応サポート」の三拍子(予防・補償・回復)をそろえたリスクマネジメント企業こそ必要とされているのではないかと仮説を持っています。
とはいえ、保険業界なので規制要件や参入コストは依然高いです。しかし逆の見方をすれば参入障壁が高い、競争が生まれにくい業界とも言えます。大手との競争リスクも当然ありますが、協業できる余地も十分にあるとも思っています。保険加入率が世界に比べかなり高い保険大国日本において、千載一遇の規制改革のタイミングが来ていることは間違いないため、非常に注目しています。
【海外スタートアップ事例】
・Stoik
中小企業向けにサイバーセキュリティ特化のソフトウェアと保険を提供し、脆弱性評価とセキュリティ体制の継続監視を行う。サイバー被害にあった際に連絡できるホットラインも提供。a16zなどからシリーズBで約40億円を調達。わずか3年でサイバーセキュリティ保険市場で圧倒的地位を確立
・ANZEN
ほとんどの企業が加入必須の保険、取締役および役員(D&O)賠償責任保険を根本から再構築する。従業員のコンプライアンスを追跡および可視化する安全監査SaaSと保険を提供する、経営リスク特化のリスクマネジメント企業。a16zと三井住友海上や東京海上も資本参加。
・RAINBOW
飲食店や美容院、ジムなどの小規模企業に特化した保険を提供。保険のリスク査定にデータとAIを活用し、適切に報告した保険契約者と代理店にインセンティブを与える設計。レストラン業界向けに特別設計された認定事業主保険が急速に成長。累計約30億円を調達。
・Alan
UI/UXに拘ったフランスのデジタル医療保険会社。医療保険はもちろん、医師が審査したAIチャットボットや健康関連製品を購入できるモバイルショップを提供。2024年時点で70万人の顧客がおり、800億円の売上。販売プロセスでもAIを活用し、営業の業績が約50%増加したとのこと。
・AgentSync
保険代理店やブローカーと保険会社をシームレスに接続し、代理店登録・ライセンス管理の自動化、行政当局への報告・更新作業の効率化を行うプラットフォーム。年間経常収益(ARR)を3倍に、顧客数を2倍に急増させるなど、目覚ましい成長を遂げている。累計約150億円を調達。
【起業アイデア例】
・法人向け領域特化の予防・保険・回復を一括対応するリスクマネジメントサービス
・法人向け領域特化のリスクコンサルティングと保険ブローカービジネス
・保険代理店のM&Aロールアップ×AIを活用したDX
Others(その他)
Personal AI Worker
AI Personal Workerとは、大規模言語モデルなどの先端技術を用い、個人や中小企業の資産運用、経理処理、学習支援、健康管理、各種事務作業などを効率化・自動化する、まさにAI秘書です。
従来は富裕層向けにのみ提供されてきた個人秘書やコーチ、あるいは税理士や弁護士などの知的サービスを、AIを活用することで一般の人々に広く届けることができるようになると信じています。
日本市場においては、少子高齢化や労働力不足、さらには企業や自治体のDX推進などを背景に、AI Personal Workerが大きな注目を集める可能性があります。
特に資産運用、税務・会計、教育、ヘルスケア、産業現場の専門領域などは、既存のAIソリューションがまだ十分に普及していないため、スタートアップが先行者メリットを得やすい可能性があります。これらの伝統的知的サービス産業におけるAIは非常に注目する一方で、GoogleやMicrosoftをはじめとする海外大手企業の寡占化リスク、海外AIスタートアップとの競争、AI人材や研究開発リソースの不足、医療や金融など規制が厳しい分野での展開の難しさなど、多くの課題もあります。
この領域では、OpenAIなど海外プレイヤーのモデルを活用しながら高品質の日本語データでファインチューニングし、法規制や商習慣に即したローカライズを行うことが現実的です。また、医療・金融などハイリスク分野の場合は専門家と法務面で連携し、誤作動やデータ漏洩を防ぐ体制を整えることが不可欠となります。さらに、ユーザー企業や個人に向けてはセキュリティ認証や個人情報保護の仕組みを明確化し、利用者が「安心してデータを預けられる」環境を提供する必要があります。
総合的に見ると、AI Personal Workerは日本が抱える構造的課題を解決できるポテンシャルを備えつつも、海外大手や国内の競合プレイヤーとの争いが激化することが確実な市場です。逆に言えば、規制への深い理解や日本語・日本文化に即したきめ細かなサービス提供ができれば、大手が参入しづらいニッチ市場を押さえるチャンスも依然として存在するでしょう。最終的な勝ち筋は、技術力だけではなくユーザー体験や法対応、独自ドメインへの特化といった複合的な差別化を戦略的に進められるかどうかに懸かっていると思っています。
Luxury Entertainment
コロナ過以降、円安も追い風となり、インバウンド観光は過去最高の水準を更新しており、世界の富裕層も日本を訪れています。2025年は大阪・関西万博も開催予定であり、日本の知名度はますます向上していくと思われます。長期的にも東南アジアやインドの生活水準の向上と人口増により、世界の観光者の3割超がこれらの国の人々になるとの予測があり、日本は中長期の観光産業において地理的に有利なポジションに位置しています。安全で、美しい海の南国からパウダースノーの雪国まで体感できる、世界的に見ても稀有な観光資源を誇る日本の強みを活かせる領域だと考えています。
一方で、特に海外の観光客や富裕層が好む長期滞在型ヴィラやオールインクルーシブリゾートといった高級宿泊施設、さらに没入型ドームを活用したスポーツ・エンタメ複合施設など、海外の方の旅行のスタンダードにマッチするコンテンツは日本ではまだ数少なく、このギャップを埋める起業やスタートアップ投資に大きな伸び代があると考えています。
オーバーツーリズムの問題もあり、京都ではホテル代が高騰している一方で、海外観光客による日本の民泊利用率は情報の非対称性の問題で非常に低いです。
他国事例としては、欧州や米国などでアーリーステージの企業がバケーションレンタルや高級民泊、富裕層向け不動産運営サービス、最先端エンタメ施設を展開し、多額の資金調達をしています。
・Emerald Stay:欧州リゾート地の高級別荘を統一基準で運営し、高品質を維持しながら収益化
・Wander:リモートワークに対応したヴィラを揃えてブランディング
・COSM:先端映像技術を取り入れたスポーツやライブ観戦の没入型エンタメ施設
こうした事業はいずれも、ハードウェア開発とソフトウェア運営を融合することで差別化を図るアプローチが共通していますが、これらに日本の地方の観光資源や日本独自の文化(温泉、伝統芸能、和食、アニメ、漫画など)を組み合わせることで、海外の富裕層にとって唯一無二の体験価値を提供できる可能性があると考えています。
とはいえ、長期滞在型リゾートや最先端施設の開発には、巨額の初期投資と行政・地域との調整が欠かせません。旅館業法や建築規制などの法的ハードルも高く、スケールアップのために多額の追加資金も必要になります。スポーツや音楽、芸能など既存大手プレイヤーが強い分野と協力するにも、権利関係の交渉やパートナーシップの構築も必須となります。
日本で「Luxury Entertainment」領域に挑戦する意義が大きいのは間違いないですが、ハード事業ゆえにリスクも相応に高いです。それでもやるんだと思える方と一緒に挑戦したいです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
新たな事業アイデアや起業構想を練りたい方、ぜひお気軽にご連絡ください
まだ曖昧なアイデアであっても、共に検証し、突破口を探っていくことに情熱を注いでいます。起業家の方や起業を検討中の方と共に、ビジネスの磨き込みから資金調達戦略まで幅広くサポートいたしますので、新しい挑戦に向けて、一緒に踏み出しましょう
詳しい活動は、以下のリンクからご覧いただけます:
私(田中 洸輝)について
・立教大学観光学部卒、体育会アメフト部第82代主将を務める
・2018年に東京海上日動火災保険株式会社入社。中堅企業の経営支援業務に従事。
・2020年にAccenture株式会社入社。経営戦略立案、DX、PMOに従事。
Accenture Ventures にてアクセラプログラムの運営、スタートアップと協業検討等に従事。
・副業的にSolo起業し、初年度で1.2億円収益あげるもスタートアップ的な起業を志向し、会社休眠を決断。VC主催の起業家イベントに参画する経験を経て、将来VCを設立/&起業することを決意。
・2022年に大手独立系シードVCのインキュベイトファンドへ参画。アソシエイトとして新規投資先の発掘、投資先企業のバリューアップ業務、LP Relation等のファンド業務全般を担当。
失われた30年 ~30歳のVCが目指す「日本を、世界の主役に」~
1994年生まれの私は、2025年現在30歳となり、ずっと失われた●●年と言われ続けてきた世代です。自分の子供や孫世代はそう言われない、素晴らしい時代に生まれたと感じて欲しい、そんな思いで日本の経済全体にポジティブなインパクトを与えること目指して、VCをしています。
(同い年のメジャーリーガー大谷翔平さんが、あれだけ凄いインパクトを日本に与えてくれていることは尊敬してやまないですし、同じ年に生まれただけで嬉しいですが、憧れすぎずに、少しでも追いつけるよう必死に頑張っていきたいです。)
父も母も起業家という家庭で育った私は、バブル崩壊の余波を食らって苦しんだ時期と裕福な時期を両方経験し、その中で起業家として最盛期に近づく様々な人々と起業家として苦境の時期に離れていく人々をたくさん見てきました。いい時も悪い時も、父も母も常に孤独に見えました。それは
真に心を許して、高いレベルで真剣に事業の相談が出来る相手が誰もいないように見えたからです。
そんな思いを持っていた中で、「1兆ドルコーチ」という1冊の本に出合います。 アメフトのコーチ出身でありながら、40代でビジネスの世界に入り、Apple創業者のスティーブジョブズの師(葬式でのスピーチが有名)であると同時に、グーグル創業者たちを育て上げ、アマゾンのベゾスを苦境から救ったという逸話で有名な方であり、彼が支えた起業家たちの時価総額を合算すると1兆ドル=約150兆円を超えると言われた伝説の人です。いずれ彼のようになると強く、決意しました。
また、私は「財を遺すは下,仕事を遺すは中,人を遺すを上とする」という言葉を大事にしています。では、どんな”人”が遺せたらいいのか?自分はどんな人達なら死ぬ気で支えたいと思えるのか?自問自答した結果、社会を良くするために革新しようとする大きな志を持った挑戦者や革命家=現代の起業家であるという答えに達しました。私はそんな人々が増えれば増えるほど、世界はもっともっと良くなると心から信じていますし、そんな素晴らしい起業家たちの背中を支え、父や母のように孤独に見えない、孤独にさせないようにしていきたいと考えています。
私のブログ等がきっかけで、起業するあるいはスタートアップに参画する選択肢を選ぶ人が1人でも増えるなら本望ですし、挑戦するきっかけとなる最後の一押し、諦めたくないけど心が折れそうになっている最後の支えであり続けるという覚悟を持って、日々VC業に取り組んでいます。
スタートアップや新規事業に関するご質問やご相談があれば、いつでもお気軽にお声がけください。未来を切り拓く挑戦を、共に進めていきましょう!
あなたの「種火」を未来の「燈火」へ
すでに登録済みの方は こちら