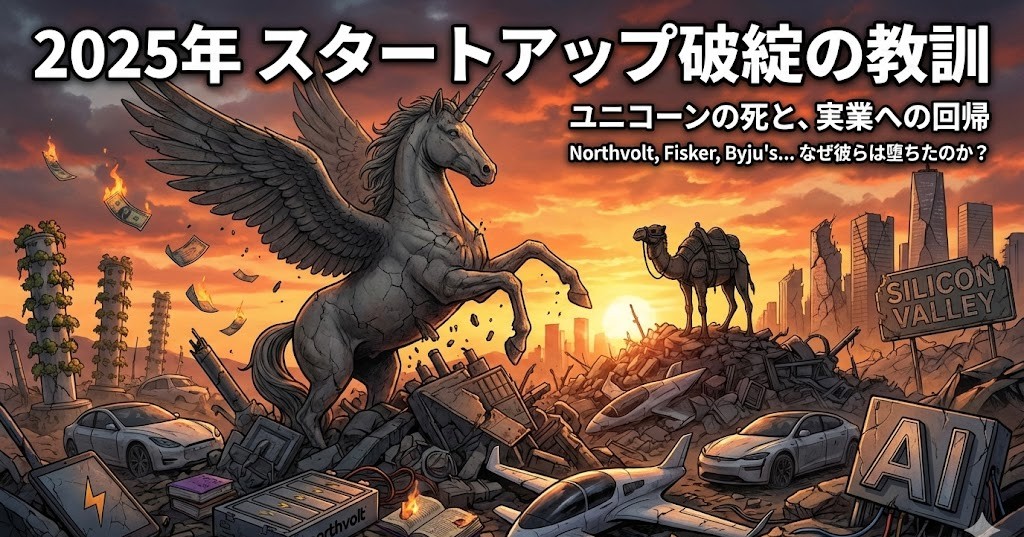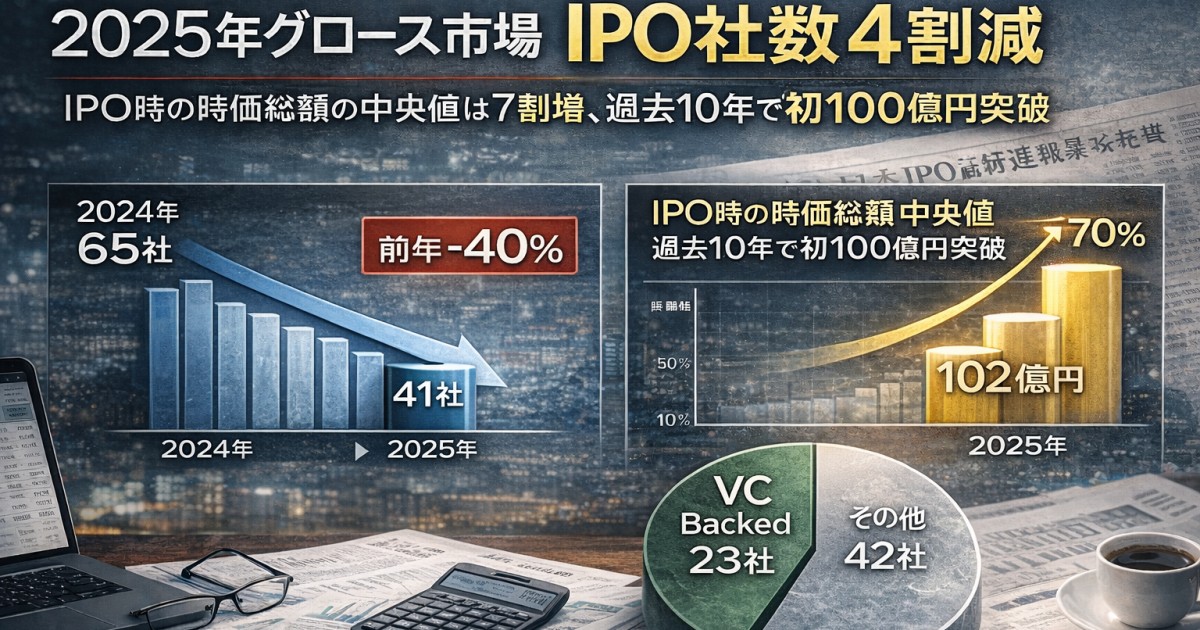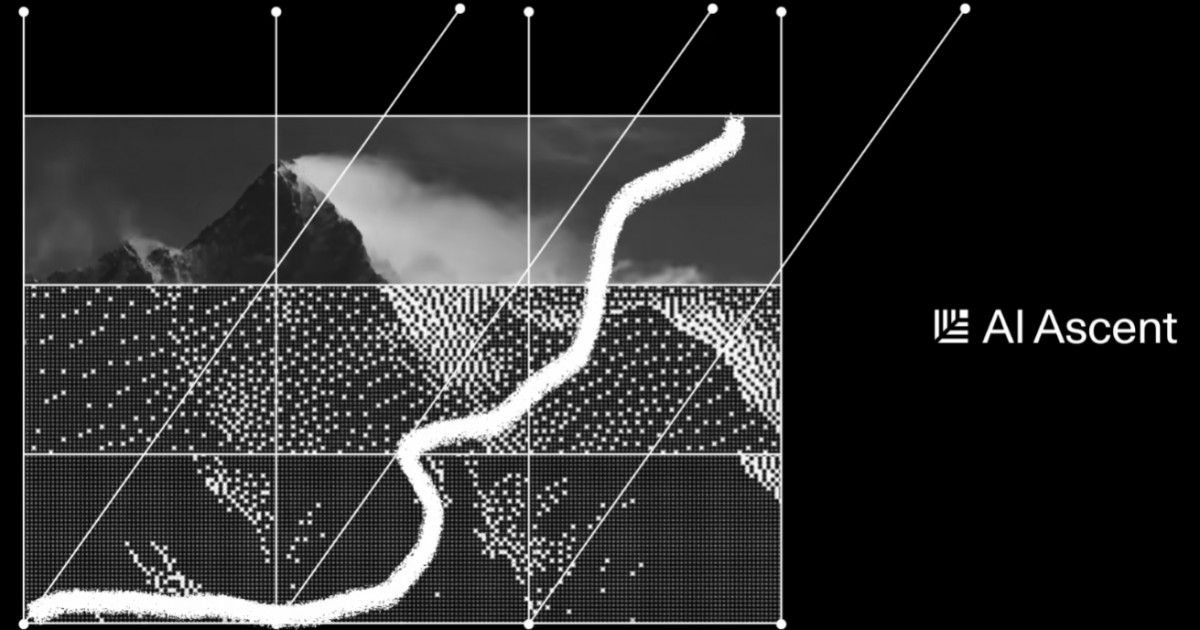「Narrative Violation」Google / Airbnb / Uber
~非常識を常識に変えた起業家たちの共通点~
目次
-
はじめに:「Narrative Violation」とは
1-1. 単なる「逆張り」はいらない
1-2. なぜ「逆説」を持つことが重要なのか -
ケーススタディ:ナラティブを覆したスタートアップ
2-1. Google:レッドオーシャンの後発検索エンジンが世界を征するまで
2-2. Airbnb:誰もが「自宅を他人に貸さない」と思い込んだ常識の破壊
2-3. Uber:規制の壁を突き破り“配車アプリ”という新ジャンルを切り拓く
2-4. Spotify:音楽ストリーミングはビジネスにならないとの悲観論を覆す
2-5. Shopify:市場が小さすぎるとの既成概念を打破した市場参入戦略 -
「Why Now?」の視点:先駆者の失敗理由を見極める
3-1. 技術革新とタイミング
3-2. 規制変化と社会情勢の変化 -
まとめ:逆張りと逆説の違い
4-1. 当初「ありえない」と言われたが故に築けた巨大市場
4-2. 逆張りだけで終わった失敗例――単なるトレンドでニーズ不在
1. はじめに:「Narrative Violation」とは
スタートアップの世界には、“王道シナリオ”が存在します。たとえば「大きな市場×優れたチーム×VC資金調達」という定石があります。しかし、その一方で、定石に沿わない、常識にとらわれないアイデアやアプローチで市場を根こそぎ変えていった企業が存在します。
この「“当たり前”に挑む」スタンスを、「Narrative Violation(ナラティブ・ヴァイオレーション)」と呼びます。大多数が信じる“通説”や“定石”(ナラティブ)を疑い、その背後にある盲点を突き止め、新たなビジネス機会に変換する思考法です。
-
既存大手や成熟市場の常識を疑う
-
長年の習慣や規制、技術的な壁が絶対だとされてきた領域を狙う
-
周囲が「それはおかしい」「成功しない」と懐疑的な領域にこそ挑戦する
本稿では、世界的に成功したスタートアップの具体例を取り上げ、いかに彼らが従来のナラティブを覆し、巨額の企業価値を創造したのかを見ていきます。そのうえで「Why Now?」の重要性や、リスクとリターンのバランスをどう捉えるべき検討しています。
1-1. 単なる「逆張り」はいらない
「Narrative Violation」という言葉を初めて聞くと、「世間がイエスならば自分はノーと言う」という単なる“逆張り”と混同されるかもしれません。しかし、これらは似て非なるものです。
単なる逆張りはあくまで世間と反対意見を取ること自体が目的化しやすく、「逆である」ことが価値と思い込むと、顧客ニーズや技術の根拠から離れたただの偏屈に陥るリスクがあります。
一方、「Narrative Violation」であることは、徹底した調査やデータに基づいた深い思考や独自の洞察に基づいて「他者がまだ発見していない真実」=「逆説」を見出すことにあります。その結果、大多数の人が避けようとするアプローチをとる場合も多いでしょう。その判断は単なる“逆張り”ではなく「この世界は本当はこう動いているかもしれない」という確信とデータを伴うものです。
1-2. なぜ「逆説」を持つことが重要なのか
大企業や多くの人が“理解しやすい”ストーリーを好む中で、スタートアップが根本的差別化と大きな価値を得るには、誰もが“困難”だと思う領域を狙うほうが合理的です。多くの人が賛同するストーリーはスタートアップだけでなく、大企業も参入しやすく、リターンが圧縮されがちだからです。
ただし、多くの人にとっては「困難な領域=儲かりにくい or 参入障壁が高い or 実務が面倒すぎる」といった固定観念が存在するケースが多いでしょう。だからこそ「なぜこの領域で誰も成功していないのか?」という疑問を一度立ち止まって問い直し、先行していったスタートアップたちが失敗した、あるいはこれまで参入しなかった理由を明確にすることが重要です。その失敗の理由こそ、逆に言えば成功するための必要条件であり、それらの解消要因となる社会変容/規制緩和/技術革新/実務遂行=隠れた真実を見つけることが、「Narrative Violation」の根源となります。
2. ケーススタディ:ナラティブを覆したスタートアップ
ここからは、実際に成功を収めたスタートアップの事例を深堀りします。いずれも当初は「そんなものは上手くいくわけがない」と言われながら、巨大市場を手に入れ、世界を変えています。
2-1. Google:レッドオーシャンの後発検索エンジンが世界を征するまで
▍飽和状態の検索エンジン市場
1990年代末、検索エンジンはYahoo!やAltaVista、Exciteなど多数のプレイヤーが激しく競合していました。すでに「検索エンジン市場は飽和している」と言われ、後発のスタートアップが入り込む余地はほとんどないと見られていたのです。また、インターネット黎明期では「検索は単なる付随サービスで大きな収益源にはならない」というのが一般的で、Yahoo!などは検索よりもポータルサイトとしてユーザーを自社内に留める戦略を重視し、検索はユーザーを他サイトに逃がしてしまうと考えられており、戦略としてナンセンスというのが常識でした。そこに登場したのがGoogleでした。
▍検索エンジンは儲からないし、成功しない?
Google以前に登場した、AltaVistaやInfoseek、Lycosなど数多くの検索エンジン系スタートアップは、いくつかの要因で十分な成功を収められませんでした。第一に、技術面ではインターネットの爆発的拡大に対し、検索アルゴリズムの革新が追いつかず、関連性の低い検索結果やスパムが蔓延してしまったのです。多くのサービスが検索精度向上よりも自社で顧客を囲いこむポータル戦略に注力したため、ユーザー満足度が向上せず、他サービスへの流出が止まりませんでした。第二に、ビジネスモデル面では検索サービス単独での収益源確立が難しく、当時はバナー広告やインプレッション課金型広告が主流でしたが、クリック率が低く効率的ではありませんでした。
▍PageRankの発明:リンク構造に基づくアルゴリズム
インターネットの拡大に伴い各社の検索精度が悪化していく中、Googleの創業者であるラリー・ペイジとセルゲイ・ブリンは、「インターネット上で重要なページは、他サイトから多くのリンクを受けているはずだ」という仮説を立て、“PageRank”と呼ばれるランキング手法を発明しました。当時の常識であった「検索キーワードの出現頻度」で結果を並べるやり方とはまったく異なり、「リンク構造そのものがwebの評価軸になりうる」という着眼点が革新的でした。その結果、劇的に関連度の高い検索結果を提供でき、瞬く間に「検索と言えばGoogle」という地位を確立しました。
とはいえ、検索利用者が急増してもGoogleも当初は収益化に苦戦しましたが、広告モデル「AdWords」を生み出し、ユーザーにとって関連性の高いテキスト広告だけを表示する仕組みを構築したことで、クリック率と広告価値が飛躍的に向上し、検索と広告が相乗効果で成長しました。
▍「レッドオーシャン後発→勝ち目なし」の常識を覆す
他社と同じやり方(キーワードベース)で検索エンジンをつくっても、先行優位を持つ企業には勝てません。しかし、Googleは全く別のアルゴリズムを採用し、その検索結果の精度とスピードによって急成長。検索市場の圧倒的トップとなっています。レッドオーシャンに後から参入しても「技術や発想が根本的に違う」ならば大勢をひっくり返せる可能性があるという好例です。
2-2. Airbnb:誰もが「自宅を他人に貸さない」と思い込んだ常識の破壊
▍宿泊は「ホテルか、せいぜいB&Bまで」という常識
Airbnbの創業者たちが注目したのは、世界規模で見れば空いている部屋や家が大量に存在する事実です。しかも従来のホテルと比べて立地や家賃が柔軟であるうえ、ユニークな個性があり、ゲストにとっては“ホテルにはない体験”が得られる可能性があります。
しかし、Airbnbが創業した2008年当初、ホテルや宿泊施設業界は「Booking.com」や「大手チェーンホテル」が中心を占め、個人宅を旅行者に貸すなんて考え方は“あまりにもリスキーだと思われていました。要するに「他人を自宅に泊めるサービスは広がらない」という常識でした。
「見知らぬ他人の家に泊まるのは危険で需要は限定的」「ホテル以外の宿泊はせいぜいB&B(民泊)やカウチサーフィンなどニッチ」というのが常識でした。Couchsurfingのようにホストの善意による無料滞在コミュニティは存在したものの、本格的なビジネスモデルはありませんでした。
▍「レビュー×本人確認×ホスト保証」=信頼のデザインが成功要因
Airbnbは、他人を自宅に泊めたくないなら「宿泊者とホストに宿泊前に安心感を持たせる仕組みを構築すれば良い」と考えました。ゲスト・ホスト双方の徹底した本人確認(身分証やSNS連携)、顔写真や詳細プロフィールを充実、相互レビューシステム、ホストへの支払保証制度などを導入し、初対面同士でも信頼関係を築ける仕組みを作りました。これにより、「知らない人の家に泊まるのは怖い」という認識を転換しました。2008年の景気後退期にローンチし、人々の経済観念の変化(節約志向・副収入志向)にマッチした点やFacebookの普及という社会変容(宿泊者と家主が繋がりやすくなっていたこと)もAirbnbにとっては追い風となりました。研究でもレビューが3件以上あるホストは信頼度が飛躍的に向上することが分かっています。これらはなんら新しい技術ではありませんが、「初対面の個人同士で宿泊取引を成立させる」ためのイノベーションとして極めて重要でした。
▍メガホテルチェーンを凌ぐ時価総額の企業へ
Airbnb以前に民泊ビジネスを試みた企業の失敗要因は、「信頼性の確保」でした。ゲスト・ホスト間のトラブル(盗難や破損、近隣迷惑など)のリスクや責任の所在が不明確で、利用者が不安を拭えなかったのです。Airbnbは上述のように技術的手法で信頼性問題に対処し、保険や保証で万一の場合の安心材料も提供しました。
結果として、Airbnbは世界中の旅行者にとって「ホテルではない選択肢」を当たり前にし、従来の宿泊産業の構造を変えました。シェアリングエコノミーの代表格として、「信頼の可視化」によってナラティブを打破した成功例です。大手ホテルチェーンの合計時価総額を上回る企業へと成長し、まさに「誰もがありえないと思った行動パターン(自宅を他人に貸す)を常識に変えた」好例です。
2-3. Uber:規制の壁を突き破り“配車アプリ”という新ジャンルを切り拓く
▍タクシー業界は新規参入不可能?
Uberが登場する以前、タクシー業界には「配車サービスは規制が厳しく新規参入は困難」「見知らぬ個人の車に乗るのは安全面で問題があり利用者に受け入れられない」といったナラティブが存在していました。各都市のタクシーは台数規制や免許制(いわゆるメダリオン制度)によって保護され、サービス品質が低く、料金も割高であることが多かったにもかかわらず、新興企業がこの既得権益に切り込むのは難しいと考えられていました。利用者側も「タクシーを呼ぶのにわざわざ新しいアプリを使うメリットはない」と思い込んでいた時代でした。
▍スマートフォン×GPS×リアルタイム配車の破壊的イノベーション
Uberの成功を支えた要因の一つは、スマートフォンとGPSを活用したオンデマンド配車という技術的イノベーションです。Uberは、スマートフォン(iPhone4S)へのGPS機能が搭載されたタイミングを捉え、乗客の需要とドライバーの供給をリアルタイムにマッチングするプラットフォームを構築し、従来の電話配車や流し営業に頼るタクシー業界を一変させました。従来のタクシーよりも安く、かつ配車がワンタップでできる便利さを武器に、一気に世界に拡大しました。もちろん各地で既存タクシー業界との衝突や法規制の問題が起きましたが、それでもユーザー体験の圧倒的な良さによってサービスは普及、配車アプリという新ジャンルを確立しました。
▍技術革新と潜在欲求の波に乗り、規制の壁を潜り抜ける
Uberは規制に正面から挑むのではなく、グレーゾーンを突き、利用者の支持を背景に規制緩和を勝ち取りました。これにより、既存のタクシー業界の構造を根本的に変革し、「新規参入は不可能」というナラティブを打破したのです。「タクシー業界は参入障壁が高い」と言われる状況であっても、技術進歩(スマホGPS)を活用して消費者の潜在欲求(より安く、便利に乗りたい)に刺さるサービスが構築できれば、圧倒的成長が出来ると証明したのがUberです。また、当初Uberの最大市場規模(TAM)=既存タクシー市場と思われていましたが、「直ぐに配車されるなら公共交通機関ではなくUberに乗る」人が圧倒的に増え、当初想定されていたTAMを遥かに凌駕して成長しました。
2-4. Spotify:音楽ストリーミングはビジネスにならないとの悲観論を覆す
▍「音楽は所有するもの」という既成概念
Spotifyが登場する前、音楽業界には「デジタル音楽配信は海賊行為(違法ダウンロード)の横行でビジネスにならない」「消費者はもはや音楽にお金を払わない」という悲観的ナラティブが広がっていました。Napster(1999年)の登場以降、CD売上は年々減少し、レコード会社はネット上の音楽共有を海賊行為=脅威とみなして法的措置に走っていました。合法的な音楽配信サービスも皆無ではなかったものの、iTunesによる曲単位購入(ダウンロード販売)が目立つ程度で、定額制ストリーミングはほぼ未知のビジネスモデルだったのです。Rhapsodyなど月額制サービスもありましたが、楽曲数や使い勝手の制限から主流にはなれず、「音楽ストリーミングは成立しにくい」という見方が強固でした。CD売上の減少とともに、音楽配信サービスは次々に失敗しており、レコード会社もストリーミングへの移行に慎重な姿勢を取っていました。
-
違法ダウンロードの台頭:NapsterやKazaaなどのP2Pサービスが無料で音楽を入手できる環境を作り出し、合法サービスの成長を阻害。
-
ライセンス交渉の失敗:Rhapsodyなどの音楽ストリーミングサービスは、大手レーベルと包括的なライセンス契約を結べず、楽曲のラインナップが不十分だった。
-
UXの未成熟:既存のストリーミングサービスは再生の遅延やインターフェースの複雑さが問題となり、普及が進まなかった。
▍UI/UXの革新:高い技術力による圧倒的なユーザー体験向上がドライバーに
Spotifyの成功には、優れたユーザー体験の提供が不可欠でした。違法ダウンロードの楽曲が蔓延する中、それはつまり「人々は豊富な曲に自由にアクセスしたがっている」ことを示していると捉え、Spotifyの創業者Daniel Ekは「ユーザー体験で海賊版に勝つ」ことを目標に掲げました。
すなわち、無料で手に入る違法音源より便利で快適なサービスを提供し、まずユーザーを惹きつける戦略です。そして彼らは、音源データ圧縮と独自のネットワーク技術により帯域負荷を最適化した結果、待ち時間ほぼゼロで楽曲を再生できる滑らかなインターフェースを実現しました。その使い勝手は当時他に類を見ないほど洗練されており、「Spotifyの音楽プレイヤーは現存するどのソフトより優れている」と評されるほどでした。また、Spotifyはプレイリスト共有やレコメンデーションなどソーシャル機能も充実させ、単なる音楽配信以上の価値を提供し、違法ダウンロードでは得られない快適さと楽しさをユーザーに感じさせることに成功したのです。技術的ブレイクスルー自体はアルゴリズムの新発明ではなく、既存技術の高度な統合とUI/UX面での工夫でした。しかし、それこそがユーザーが求めていたものであり、「使い勝手が悪ければ海賊版に流れる」というジレンマを打破する決め手となりました。
▍先駆者の失敗の理由を解消する「ビジネス戦略」と「プロダクト戦略」の両立
音楽配信ビジネスの先駆者たちは、技術か規制の壁で挫折を味わいました。Napsterは技術的には画期的でしたが違法性が仇となり消滅し、RhapsodyやPandoraはコンテンツ量や機能の制約からユーザーを広げられませんでした。
Spotifyの最大の成功要因は、「音楽業界構造を変えるビジネスアプローチ」と「妥協のないユーザー体験」の両立でした。中でも決定打となったのは前者、すなわち主要レーベルを巻き込んだライセンス戦略です。Spotifyは先駆者の事例を踏まえ、「レーベルを敵ではなく味方にする」戦略に打って出ます。その象徴が前述の株式提供による包括契約です。さらに、サービス開始後もアーティストやレーベルに十分なロイヤリティを還元する仕組み(ストリーム数に応じた収益分配)を整え、業界内の信頼を維持しました。技術面でも、Napster世代が犯したUIの甘さを改善し、誰もが直感的に使える優れたデザインを提供したことでユーザーの心を掴みました。このように先行者が犯した過ちを回避し、必要な要素を満たすことで市場の物語を塗り替えることに成功したのです。
2-5. Shopify:市場が小さすぎるとの既成概念を打破した市場参入戦略
▍小規模事業者向けのECサイト支援など需要がない?
Shopifyが挑んだのは「小規模事業者が自前で本格的なオンラインストアを構築するのは難しい」「そもそも小規模事業者の数が少なく市場が存在しない」という通念でした。2000年代前半まで、ネットショップを開くには専門的な知識や多額の費用が必要であり、個人店主や中小企業には高いハードルがありました。創業者はスノーボード通販サイト立ち上げで既存ソフトの使い勝手の悪さに失望した経験を語っています。当時のツールは時代遅れで融通が利かず、多くの小規模事業者にとってネット進出を断念するボトルネックとなっており、創業者自身がそれを体感していたことが顧客の潜在需要や市場の大きさを確信できた理由でした。
▍社会トレンドの急速な追い風×顧客思考に立脚したプロダクト
Shopify以前にもECサイト構築サービスは存在しましたが、大半は限定的な成功に留まりました。その失敗・停滞の要因は以下の通り、多岐にわたりました。
・使い勝手:UIが複雑で小事業者は専門家に委託せざるを得なかった
・拡張性:汎用ECソフトの画一的な機能では、小規模ニーズに対応できない
・運用負荷:顧客側で自前サーバーを動かす必要があり、高い負荷とリスクがありました
・収益モデル:売り切りの高額な初期費用でベンダー側も機能拡張する気はありませんでした
Shopifyは上記を解消し、(AWSの進化もありましたが、)顧客のニーズに対応したプロダクトを、サブスクリプションや成功報酬の顧客に寄り添ったビジネスモデルで提供しました。
また、起業・副業ブームとD2C(Direct to Consumer)トレンドの追い風に乗ったことも非常に大きな成功要因でした。2010年代に入ると、個人や小さなチームが自社ブランド商品を企画・製造し、ネットを通じて直接消費者に売る動きが世界的に活発化しました。SNSの発達で広告宣伝が低コストでできるようになり、小規模でもニッチな市場で成功する事例が増えました。「誰もがオンラインでビジネスを始められる時代」が到来しつつあったのです。Shopifyは当初D2Cブランドの立ち上げ支援プラットフォームとして支持を集めました。
▍社会変容×技術革新の波に乗り、市場の独占企業へ
Shopifyは創業者自身が顧客と同質性が高く、D2C市場が急成長するという社会の変化をいち早く体感できていたため、D2C市場が急拡大した未来に必要なプロダクトをいち早く構築できていたことが成功要因となりました。
Shopifyは非エンジニアのビジネスオーナーが自力で操作できるほど平易な管理画面と、テンプレート適用だけで見栄え良く作れる設計を実現しました。この「誰でもできる」を追求したプロダクトが、従来の常識「専門知識がないとネットショップは作れない」を打ち破ったのです。使い方ガイドやEC成功事例の共有、顧客サポートの手厚さなど、単なるソフト提供企業の域を超えた伴走支援も行っており、顧客企業との強い信頼関係を築き、「Shopifyと一緒ならネットショップで成功できる」という新たな物語をも作り出しました。この信頼がユーザー拡大の連鎖を生みました。
「市場が小さすぎる」と多くの投資家に断られましたが、現在では175か国以上で数百万のストアがShopify上に存在し、累計流通総額は5,430億ドルを超える規模に達しています。
3. 「Why Now?」の視点:先駆者の失敗理由を見極める
ナラティブを覆す挑戦は常に可能なわけではなく、そこには必ず「Why Now?」タイミングの妙があります。上記の事例からわかるように多くのスタートアップは過去の先駆者の失敗理由や困難であると思われる背景を分析し、それらが当時の技術や社会情勢、規制環境の変化で解消できるタイミングを巧みに捉えて非連続な成長を実現しています。単なる逆張りではなく、なぜ今の社会/規制/技術なら成功できると思うのかの「逆説」(アンチテーゼ)を持つ事が重要と気づかされます。
3-1. 技術革新と社会実装の閾値
-
UberやLyftが急成長した背景には、スマートフォンのGPSや決済システムが「十分に普及してから」というタイミングがあります。
-
SpaceXであれば、コンピュータシミュレーションや材料工学の進歩を活用し、ロケット開発のコスト削減が現実的になったタイミングを捉えました。
このように、多くの人が「新技術はどこかでブレイクするだろう」と思っていても、実際に本当に活用される、実用化する段階を見定められるかが勝負です。
3-2. 規制変化と社会情勢の変化
-
AirbnbやShopifyの拡大を支えた要因には、インターネットの普及、2008年の金融危機後、人々が副収入を求めるようになったといった複数の社会的背景があります。
-
TeslaのEVシフトを後押ししたのは、環境規制や脱炭素への国際的な流れでした。
これらの変化を正確に見極め「なぜ今こそこれが普及するのか」の仮説(逆説)を明確化することが大切です。
4. まとめ:逆張りと逆説の違い
4-1. 当初「ありえない」と言われたが故に築けた巨大市場
上述したGoogle、Airbnb、Uber、Spotify、Shopifyなどはいずれも“常識”によって参入障壁が高いと見られていたり、“そんなサービスは市場がない”と切り捨てられていたりしました。それが故に、結果的に競合が少なく、従来の大手プレイヤーも真剣に対抗策を取らなかったため、大きな市場を一気に握ることができたのです。「Narrative Violation」の魅力は、真に価値ある新市場を独占できる可能性にあります。もし自分たちの見立てが正しければ、既成概念に縛られた大企業が追随してくる頃には、既に決定的なリードを得られているでしょう。
4-2. 逆張りだけで終わった失敗例――単なるトレンドでニーズ不在
一方、注意すべきは「非常識」であれば何でもチャンスになるわけではないということです。ブロックチェーンやCrypto、ClimateTechなど、期待値が急上昇したテクノロジーの領域では数多くのスタートアップが生まれましたが、その多くが「市場ニーズ」や「実証データ」を欠き、とにかく競合と異なることをやるという“単なる逆張り”に終わって資金ショートしています。これらの領域がダメなわけでは一切なく、これらの領域においても社会/規制/技術/実行に基づく、明確なWhy Now(成功仮説や逆説)がある企業は成功を収めています。
大きなイノベーションを起こすには、上記のように「誰もまだやっていない」というよりは、「過去にチャレンジした人たちはいた」ものの、「なぜ上手く出来なかったのか」を丁寧に紐解き、そこから本質的な突破口を見出すことが重要だなとケースをそれぞれ分析していると感じます。
多くの起業家の方は、新たな事業を検討するとき、もし周囲や投資家から「そんなの上手くいくはずがない」と言われたなら、それを単なる批判とみなさずに「なぜそう思われるのか」を徹底的に分析してみてください。その“否定の根拠”こそが既存のナラティブの正体であり、そこにこそ大きな突破口が潜んでいる可能性があります。誰も振り向かないうちに仕込み、世界を塗り替えるチャンスをつかむ――それが「Narrative Violation」の真髄です。
一緒に、逆説を考えたい方、是非議論させてください。
日程調整URL:https://meetings.hubspot.com/koki-tanaka
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーこの記事が少しでも皆様のお役に立てば幸いです!
新たな事業アイデアや起業構想を練りたい方、ぜひお気軽にご連絡ください
まだ曖昧なアイデアであっても、共に検証し、突破口を探っていくことに情熱を注いでいます。
起業家の方や起業を検討中の方と共に、ビジネスの磨き込みから資金調達戦略まで幅広くサポートいたしますので、新しい挑戦に向けて、一緒に踏み出しましょう
URLから直接日程調整も可能です
Facebook:https://www.facebook.com/CoolWimps/
Twitter:https://twitter.com/k4oki
すでに登録済みの方は こちら